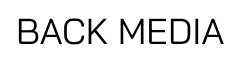近年、M&Aは企業の成長戦略や円滑な事業承継の有効な手段として広く活用されています。しかし、その一方で、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクも存在します。これらのトラブルは、手続きの不備や情報の誤認、契約条件の曖昧さなど、さまざまな原因で発生し、経営全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
売却価格に関する交渉の難航、デューデリジェンスで問題が発覚し白紙撤回に至るケース、買収後の従業員や取引先の混乱、想定していた収益が得られない、さらには情報漏洩や詐欺、特に経営者保証が解除されない「ルシアン事件」のような悪質な事例も報告されています。
これらのトラブルを回避し、M&Aを成功させるためには、事前の準備を徹底し、リスクを正確に把握することが不可欠です。
本解説では、具体的なトラブル事例とその原因を掘り下げ、徹底したデューデリジェンスや正確な情報開示、適切な契約書の作成、そして信頼できる専門家のサポートといった、トラブルを回避するための具体的な対策を詳しくご紹介します。M&Aを安全かつ円滑に進め、企業の未来を守るための知識として、ぜひ本解説をご活用ください。
M&Aトラブルの解決を弁護士に依頼する7つのメリットと必要性
M&Aトラブルが発生した場合、またはその可能性が高いと判断される場合、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートは極めて重要です。弁護士は、紛争の予防から解決まで、M&Aの全プロセスにおいて不可欠な役割を果たしますので、M&Aの時系列に沿って解説します。
法的リスクの洗い出しと未然防止
M&Aトラブルにおいて弁護士が果たす最も基本的な役割は、法的リスクの洗い出しとその未然防止です。M&Aは複雑な法規制が絡むため、契約書の内容や手続きの進め方に不備があると、後に重大なトラブルに発展するリスクがあります。
弁護士は、法務デューデリジェンス(法務DD)を通じて、対象企業の契約関係、知的財産権、訴訟・紛争、規制遵守状況などを多角的に調査し、潜在的な問題点を事前に特定します。これにより、買収後に想定外の債務や訴訟リスクが発覚する事態を防ぎ、経営上の大きな損失を回避できます。
また、弁護士は金融商品取引法や独占禁止法など、M&Aに関わる各種法規制の遵守状況も確認し、適法な取引の実現に寄与します。法的リスクの早期発見と対策は、M&Aの成否を左右する重要なポイントであり、弁護士の専門知識が不可欠です。
契約書作成・レビューによるトラブル防止
M&Aにおける契約書は、取引の根幹をなす極めて重要な書類です。最終契約書や秘密保持契約(NDA)など、複数の契約書が必要となり、その内容に曖昧さや不備があると、M&A後に解釈の相違や履行トラブルが発生する原因となります。
弁護士は、契約書の作成や内容の精査を通じて、法的に有効かつ依頼者にとって不利な条件が含まれていないかを徹底的にチェックします。
特に、表明保証条項や補償条項、違約金条項などM&A特有の条項について、豊富な経験と知識を活かしてリスクを最小化します。これにより、契約締結後の紛争リスクを大幅に低減し、安心して取引を進めることが可能となります。
法務デューデリジェンス(DD)の実施
M&Aトラブルを防ぐためには、対象企業の法的状況を徹底的に調査する「法務デューデリジェンス(DD)」が不可欠です。
弁護士は、契約書、訴訟・紛争、許認可、知的財産、労務・雇用関係など、企業が抱える法的リスクを多角的に調査・分析します。法務DDの結果は、買収価格の算定やM&Aの実施判断に直結するため、専門家による精緻な調査が求められます。
弁護士が主導することで、重大な訴訟リスクやコンプライアンス違反など、経営に大きな影響を与える問題を事前に把握し、適切な対策や条件調整が可能となります。これにより、買収後の「知らなかった」リスクを最小化できます。
交渉代理・調整役としての機能
M&A交渉は、売り手・買い手双方の利害が鋭く対立する場面が多く、交渉過程でのトラブルや感情的な対立が発生しやすいのが実情です。
弁護士は、依頼者の代理人として交渉に参加し、法的根拠に基づいた主張や条件調整を行います。これにより、相手企業とのパワーバランスが取れ、依頼者が不利益な条件を押し付けられるリスクを回避できます。
また、交渉過程で発生する細かなトラブルや疑義についても、弁護士が間に入ることで冷静かつ合理的な解決を図ることができ、訴訟や大きな紛争へ発展するのを防ぐ役割も担います。
各種法的手続きの適正な実施
M&Aには、会社法や金融商品取引法などに基づく多様な法的手続きが伴います。たとえば、株式譲渡や合併、会社分割などの手続きでは、公告や債権者保護手続き、登記申請などが必要となり、これらを怠ると取引自体が無効となったり、後日トラブルの原因となることがあります。
弁護士は、こうした法的手続きを正確かつ適切に進行するための支援を行い、手続きミスによるリスクを排除します。特にクロスボーダーM&Aなど、複雑な法域が絡む場合には、各国の法規制に精通した弁護士の助言が不可欠です。
紛争発生時の迅速な対応と訴訟代理
万が一M&Aトラブルが発生した場合、弁護士は依頼者の代理人として迅速かつ的確な対応を行います。契約違反や表明保証違反、情報開示義務違反など、M&A特有の紛争は複雑かつ専門性が高いものが多く、法的知識と経験がなければ適切な対応は困難です。
弁護士は、交渉による和解や、必要に応じて訴訟・仲裁などの法的手段を駆使し、依頼者の権利と利益を最大限に守ります。また、紛争の早期解決を図ることで、企業イメージの毀損や経営への悪影響を最小限に抑えることができます。
M&A後の統合・運営サポート
M&Aは成約がゴールではなく、買収後の統合(PMI:ポスト・マージャー・インテグレーション)で新たな法的問題が発生することも少なくありません。
たとえば、従業員の処遇や契約関係の承継、グループ会社の再編、知的財産権の移転など、M&A後の運営段階でも弁護士の助言や対応が求められます。
弁護士は、統合プロセスにおける法的課題を整理し、必要な契約や手続きのサポート、さらには新たな紛争の予防策を講じることで、M&Aの真の成功を後押しします。
M&A後の継続的な法的サポートは、企業価値の最大化と安定した経営に不可欠です。
M&Aトラブルに強い弁護士・法律事務所の特徴
M&A取引は複雑かつリスクの高い経営判断を伴うため、適切な法的サポートが成功の鍵となります。
近年、日本国内でのM&A取引件数は増加の一途をたどり、それに比例して関連訴訟も増加しています。2023年の統計では、M&A関連の紛争が前年比30%増加したというデータもあります。
M&Aトラブルを未然に防ぎ、または発生した紛争を有利に解決するためには、有能な弁護士の存在が不可欠です。ここでは、M&Aトラブルに強い弁護士の特徴を7つ挙げ、それぞれ詳しく解説します。
M&A専門の豊富な経験と実績
M&Aトラブルに強い弁護士の最も重要な特徴は、M&A案件に特化した豊富な経験と実績です。M&A紛争は一般的な企業法務と比較して、株価算定、デューデリジェンス不備、表明保証違反など、高度に専門的な争点が絡むため、この分野での経験がない弁護士では適切な対応が難しくなります。
大手法律事務所の西村あさひ法律事務所や森・濱田松本法律事務所のM&A部門は、年間数百件のM&A案件を扱っており、紛争解決においても圧倒的な実績を持っています。しかし、必ずしも大手事務所だけが選択肢ではなく、中規模でもM&A紛争に特化した弁護士であれば、より機動的かつ戦略的な対応が期待できるケースもあります。
弁護士選定の際は、過去のM&A紛争案件数、勝訴率、特に自社と類似する業界での成功事例を確認することが重要です。また、初期相談の段階で弁護士がどれだけ具体的な戦略を提示できるかも選定基準として有効です。「一般論」ではなく「あなたの案件ならこう戦う」という具体性のある提案ができる弁護士は、実戦経験が豊富な証と言えるでしょう。
M&A紛争は短期決戦となりやすく、初動の対応が全てを決める傾向があるため、問題が表面化した段階ですぐに専門性の高い弁護士に相談することが、裁判での勝利への第一歩となります。
財務・会計の深い理解力
M&Aトラブルに強い弁護士の二つ目の特徴は、財務・会計に関する深い理解力です。M&A取引に関する紛争で最も激しい争点となるのが「企業価値評価」であり、買収側は「高く払いすぎた」と主張し、売却側は「安く買いたたかれた」と反論する構図が典型的です。
こうした価値評価をめぐる裁判で優位に立つためには、DCF法、マルチプル法、純資産法など様々な企業価値評価手法の原理と適用限界を理解していることが必須です。例えば、東京地裁令和元年判決では、DCF法における成長率の設定ミスを弁護側が指摘し、評価額の大幅な修正につながった実例があります。
名門大手法律事務所では、会計士資格を持つ弁護士や財務専門チームを擁しているのはこのためです。財務・会計に精通している弁護士は、相手方の主張の弱点を的確に把握し、反論することができます。
また、M&Aを検討する段階でも、企業価値評価の妥当性を法的観点から検証することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。M&Aトラブルに強い弁護士は、単なる法的知識だけでなく、財務・会計の専門知識を持ち合わせており、それがM&A訴訟における重要な武器となります。
業界特性の把握力
M&Aトラブルに強い弁護士の三つ目の特徴は、業界特性を的確に把握する能力です。IT企業と製造業では価値評価の重点が全く異なるように、業界固有の価値ドライバーや事業リスクを理解していなければ、適切なM&A戦略の策定や紛争対応はできません。
優れた弁護士は、クライアント企業が属する業界の特性を深く理解し、その業界特有の法的リスクや商慣行を熟知しています。例えば、テクノロジー業界ではITシステムや知的財産権が中核的な価値を持ち、製造業では設備や生産能力が重視されます。医療業界では認可や規制対応が重要となるなど、業界ごとに重視すべきポイントが異なります。
M&A仲介において、「業界知識とリスクマネジメント」は不可欠なスキルとされており、弁護士もその専門性を持つことが期待されています。特にクロスボーダーM&Aでは、対象国の法制度及び慣習に関する専門知識が不可欠であり、外資規制を踏まえたストラクチャーの検討や外国当事者を相手方とする交渉など、国際的な視点と業界知識の両方が求められます。
業界特性を理解している弁護士は、M&Aの交渉段階で業界特有の重要条項を契約に盛り込むことができ、また紛争発生時には業界特有の観点から効果的な反論や戦略を立てることができます。
これにより、M&Aトラブルの早期解決や有利な条件での和解が可能になります。
卓越した交渉力とコミュニケーション能力
M&Aトラブルに強い弁護士の四つ目の特徴は、卓越した交渉力とコミュニケーション能力です。M&Aは交渉の連続であり、相手企業、株主、取引先、監督官庁など多くの関係者と交渉を進める必要があります。弁護士が強い交渉力を持ち、複雑な利害関係を調整できることは、M&A成功の鍵となります。
弁護士にM&A交渉の代理人となってもらうことで、相手企業に対する交渉力を補強することができます。特に、売り手企業が格上の買い手企業を相手にして交渉を行わなければならない場合には有効な選択肢です。法的知識と交渉経験を生かし、取引がスムーズに進むように支援します。
優れたM&A弁護士は、強引な交渉ではなく、Win-Winの関係を構築できる交渉を心がけます。M&Aの成功は単に契約を締結することではなく、その後の事業統合がスムーズに進むことにあるからです。このため、相手方の立場や意向を理解し、法的に問題ない範囲で妥当な解決策を提示できる能力が重要です。
また、M&Aには株主、従業員、取引先など、多くのステークホルダーが関わるため、その利害を適切に調整するスキルも必要です。弁護士は、各ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行い、M&Aに対する理解と協力を得ることで、紛争の発生リスクを低減します。
M&Aトラブルが発生した場合も、冷静かつ論理的なコミュニケーションを通じて、最善の解決策を模索することができます。
法的リスク管理能力
M&Aトラブルに強い弁護士の五つ目の特徴は、優れた法的リスク管理能力です。M&A取引における法的リスクの管理と評価は、取引の成功に不可欠な要素であり、M&A弁護士は企業が直面する潜在的な法的問題を特定し、それらを軽減するための戦略を立案します。
法的リスク管理において特に重要なのは、M&A後に発生しうるトラブルを予測し、事前に対策を講じる能力です。経験豊富な弁護士は過去の事例から学んだ知見を活かし、リスクの特定と対策立案をサポートしてくれます。M&Aを検討する際は、単に契約書作成だけでなく、包括的なリスク管理の視点が重要です。
法的リスクには、法令違反によって制裁を受けるリスクや、契約書類などの不備によって不利益を受けるリスク、訴訟や紛争などによって不利益を受けるリスクがあります。これらのリスクを事前に把握し、対策を講じることで、M&A後のトラブルを大幅に減らすことができます。
優れたM&A弁護士は、多角的な視点から問題を発見・解決する能力を持っています。単に法律問題だけを見るのではなく、ビジネス全体の戦略の中で法的リスクを評価し、適切な対応策を提案します。法的リスク管理によって、M&A後の統合過程がスムーズに進み、期待していた相乗効果を得られる可能性が高まります。
デューデリジェンスの専門性
M&Aトラブルに強い弁護士の六つ目の特徴は、デューデリジェンス(DD)の専門性です。デューデリジェンスとは、M&Aの相手先に対して行われる企業監査で、法的リスクを含む様々な観点から企業の実態を把握することを目的としています。
弁護士が担当する法務デューデリジェンスでは、売手対象会社の株主や関連会社、締結している契約などを確認し、予期せぬリスクが隠れていないかを調査します。主な確認項目としては、株式、契約、知的財産権、労務、環境、許認可、紛争・訴訟などが挙げられます。
特に重要なのは、契約におけるCOC(チェンジ・オブ・コントロール)条項の有無や、知的財産権の帰属状況、労働法関係のコンプライアンス違反の有無、係争中の訴訟・紛争などです。これらのリスクを見落とすと、M&A後に大きな損失を被る可能性があります。
M&Aトラブルに強い弁護士は、デューデリジェンスの重要性を十分に理解し、徹底的かつ効率的に調査を行います。また、発見されたリスクを適切に評価し、契約条件や買収価格に反映させる能力を持っています。デューデリジェンスへの対応力があれば、M&A後に「知らなかった」というトラブルを最小限に抑えることができ、結果的にM&Aの成功確率を高めることができます。
契約書作成・レビューの卓越した能力
M&Aトラブルに強い弁護士の七つ目の特徴は、契約書作成・レビューの卓越した能力です。M&Aでは、意向表明書や基本合意書、株式譲渡契約書(最終契約書)など、複数の重要な契約書が必要になります。これらの契約書は法的拘束力があるため、内容に不備があれば後に法的トラブルを引き起こす可能性があります。
優れたM&A弁護士は、契約書の作成やレビューを通じて、法的リスクを最小限に抑え、契約内容が適正かつ法的に問題がないかを徹底的に確認します。特に表明保証条項、補償条項、誓約条項などM&A特有の重要条項について、豊富な経験に基づいた精緻な条文作成能力を持っています。
M&A契約書は一般的な契約書と比較して複雑であり、将来発生しうる様々な事態に対応できるように詳細な条項を盛り込む必要があります。M&Aトラブルに強い弁護士は、過去の紛争事例から学んだ知見を活かし、将来の紛争を予防するための条項を適切に設計することができます。
また、契約書の不明確な記載や不十分な条件設定はM&A後のトラブルの原因となるため、明確かつ詳細な契約書を作成する能力は極めて重要です。M&A経験の豊富な弁護士は、業界特性や取引の特殊性を考慮した上で、オーダーメイドの契約書を作成し、クライアントの権利を最大限に保護します。
各種契約の法的効力のある文章を専門家に確認してもらうことで、M&A後にトラブルになるリスクを低減でき、契約書作成・レビュー能力は、M&Aトラブルを未然に防ぐための必須条件と言えるでしょう。
M&Aトラブルに強い弁護士の選び方と比較ポイント5選
M&Aトラブル解決の実績・経験が豊富であること
M&Aトラブルに強い弁護士を選ぶ際、最も重視すべきは「実務経験と解決実績の豊富さ」です。M&Aは一般的な企業法務と比較しても、取引規模が大きく、契約やデューデリジェンス、交渉、統合後の対応まで多岐にわたる専門知識と経験が求められます。
特にトラブル発生時には、過去の類似案件でどのような解決策を講じ、どれだけ依頼者の利益を守れたかが重要な判断基準となります。弁護士や法律事務所のホームページには、M&A関連の解決実績が掲載されていることが多いので、案件数や内容、業界などを比較検討しましょう。
また、直接面談時に「どのようなM&Aトラブルをどのように解決したか」を具体的に質問し、経験値や対応力を確認することも大切です。実績豊富な弁護士は、想定されるリスクや解決までの道筋を明確に示してくれるため、安心して依頼できます。
幅広い専門知識とネットワークを有していること
M&Aトラブルは、会社法や民法だけでなく、税務、会計、労務、知的財産、不動産など多様な法的領域が絡み合うことが多いです。
したがって、M&Aに強い弁護士は、これら幅広い分野の知識を持ち、必要に応じて各分野の専門家と連携できるネットワークを有していることが望ましいです。特にクロスボーダーM&Aや業界特有の規制がある場合、海外の法律事務所や専門家とのパイプがある事務所を選ぶことで、より確実な取引やトラブル対応が可能となります。
また、会計士や税理士、社労士などとチームを組んで対応できる体制が整っているかも確認しましょう。こうしたネットワークと総合力が、複雑なM&Aトラブルの早期解決や予防につながります。
コミュニケーション能力と対応力
M&Aトラブルの解決には、弁護士と依頼者との密なコミュニケーションが不可欠です。M&A案件は情報量が多く、進行中に状況が変化しやすいため、弁護士が複雑な法的内容を分かりやすく説明し、依頼者の希望や懸念を的確に汲み取れるかが重要となります。
初回相談時の対応や質問に対するレスポンスの速さ、説明のわかりやすさなどから、その弁護士のコミュニケーション能力を見極めましょう。また、トラブル対応はスピードが勝負となる場面も多いため、緊急時にも迅速に対応してくれるかどうかも大切なポイントです。
信頼関係を築ける弁護士であれば、安心して長期的にサポートを依頼できます。
交渉力・調整力の高さ
M&Aトラブルは、相手方企業や関係者との交渉が不可避です。交渉力の高い弁護士は、法的根拠をもとに依頼者の主張を的確に伝えつつ、相手方との妥協点を見出して円滑な和解や解決に導くことができます。
特に、利害が複雑に絡み合うM&Aでは、単なる法的知識だけでなく、現場での調整力や説得力、時には強いリーダーシップも求められます。過去の交渉事例や、どのようにして難航した案件をまとめたかなどを面談時に確認し、その弁護士の交渉スタンスや実績を見極めましょう。
交渉力のある弁護士は、依頼者の利益を最大化し、不要な対立や訴訟リスクを回避することができます。
業界や案件特有の専門性・マッチング
M&Aと一口に言っても、業界や案件ごとに求められる法的知識やリスクは大きく異なります。例えば医療法人のM&Aでは医療法への精通が不可欠ですし、IT企業のM&Aでは知的財産権やデジタル分野の知識が求められます。
そのため、自社の業界や案件特有の事情に精通した弁護士を選ぶことが重要です。事務所のホームページや実績紹介、初回面談で「同業界のM&Aトラブルにどれだけ対応した経験があるか」を具体的に確認しましょう。
業界特有のリスクや商慣習を理解した弁護士であれば、より実践的かつ的確なアドバイスや解決策を提示してくれます。
自社のニーズと弁護士の専門性がマッチしているかを重視することで、トラブル発生時も安心して任せられます。
M&Aトラブルの解決が強い弁護士・法律事務所
これらのオンラインプラットフォームは、地域や専門分野で絞り込んで弁護士を検索できるため、自社のニーズに合った弁護士を見つけるための有力な手段となります。
企業法務弁護士ナビ
「企業法務弁護士ナビ」は、企業法務全般に強い弁護士を効率的に検索できる日本最大級のマッチングサイトです。M&Aや法務デューデリジェンス、契約書レビュー、紛争解決など、M&Aトラブルに対応可能な弁護士を、地域や得意分野、実績、料金体系などの条件から絞り込んで探せます。
公式サイト:https://houmu-pro.com/
各弁護士のプロフィールや経歴、過去の案件実績、料金目安などが詳しく掲載されているため、自社のニーズに合った専門家を比較・検討しやすいのが大きな特徴です。相談予約もサイト上から簡単にでき、初回相談無料の弁護士も多数登録しています。
また、M&Aトラブルに特化したコラムやQ&A、弁護士選びのポイントなど情報コンテンツも豊富で、初めてのM&Aやトラブル対応で不安な方にも役立ちます。信頼できる弁護士を自分で選びたい、自社に最適な専門家を探したい場合に非常に便利な相談窓口です。
公式サイト:https://houmu-pro.com/
弁護士法人M&A総合法律事務所

弁護士法人M&A総合法律事務所は、M&A分野に特化した専門法律事務所で、これまでに400件以上のM&A案件やトラブル解決実績を持っています。M&Aの法務・業務だけでなく、仲介業務やアドバイザリー、価格算定、交渉支援などワンストップで幅広いサービスを提供している点が特徴です。
同事務所には、M&Aや交渉理論を専門的に学んだMBA弁護士も在籍しており、法務のみならず会計・税務・労務・知財などの専門家とも連携して総合的なサポートが可能です。M&Aトラブルに関しては、契約条件の不備や価格交渉、損害賠償請求、買収後の紛争など幅広い事例に対応してきた実績があります。
初回相談は電話・Webで受付けており、M&Aトラブルの内容や課題に応じて最適な弁護士が対応します。専門性の高いM&Aトラブルに直面した場合、実績豊富なプロフェッショナルに直接相談できる安心感があります。
公式サイト:https://tokyo-malaw.jp/
隼あすか法律事務所

隼あすか法律事務所は、上場企業から中小企業まで幅広いM&A案件を取り扱う大手法律事務所です。特に合併・会社分割・MBO・事業譲渡・クロスボーダーM&Aなど多様なスキームに強く、M&Aトラブルの予防や解決にも豊富な実績を有しています。
同事務所では、M&Aスキームの検討や第三者委員会の運営、契約書の作成・レビュー、法務デューデリジェンス、組織再編手続きなど、M&Aに関わるあらゆる法務サービスをワンストップで提供しています。また、公認会計士・税理士など他分野の専門家とも連携し、複雑な案件にも対応できる体制を整えています。
M&Aトラブルの相談も随時受け付けており、初回相談から具体的な解決策の提案まで一貫してサポートを受けることが可能です。特に上場企業や大規模案件、国際取引など専門性の高いM&Aトラブルに直面した場合に、信頼できる相談先としておすすめです。
公式サイト:https://www.halaw.jp/
シャローム綜合法律事務所

M&Aに伴う紛争解決を専門的に取り扱う法律事務所で、特に表明保証違反や仲介業者とのトラブルに豊富な知見を有しています。ウェブサイトではM&Aトラブルに関する判例を多数紹介しており、専門性の高さがうかがえます。
買主側、売主側双方の立場から相談を受け付けており、買収後に発覚した問題(簿外債務、従業員の引き抜きなど)や、売却後の代金未払いや損害賠償請求など、具体的なトラブル事例に応じた対応が可能です。
紛争解決にあたっては、まず弁護士が詳細なヒアリングを行い、損害の有無や法的な請求の可否を検討した上で、示談交渉や訴訟といった具体的な手続きを進めます。
全国対応を明言しており、遠方の企業でも電話やオンラインでの相談が可能です。各種メディアでM&Aトラブルに関するコメントが掲載されるなど、外部からの評価も高い事務所です。
公式サイト:https://www.manda-trouble.com/
栗林総合法律事務所

30年近い業務経験を基に、特に中小企業のM&Aを支援している法律事務所です。株式譲渡や事業譲渡といった一般的な手法から、会社分割、第三者割当増資まで、企業の状況に応じた最適なM&A手法を提案します。
この事務所の大きな特徴は、国際取引や国際紛争の解決に強みを持っている点です。英文契約書の作成や海外企業との契約交渉にも精通しており、グローバルなM&A案件におけるトラブル対応も可能です。
訴訟・紛争解決を主要な業務分野の一つと位置づけており、M&Aに限らず、企業法務全般にわたる豊富な経験と知識を活かして、紛争の本質を見極め、的確な解決策を導き出します。M&Aの実行支援だけでなく、取引後に発生した問題についても、粘り強い交渉や訴訟を通じて依頼者の権利を守ります。
公式サイト:https://kslaw.jp/baisyu/
森・濱田松本法律事務所

西村あさひ法律事務所などと並び、日本を代表する四大法律事務所の一つです。国内外の大型M&A案件において、国内トップクラスの実績を誇ります。この事務所の強みは、各分野の専門家が多数在籍する組織力にあります。
M&A関連の紛争においても、会社法、金融商品取引法、独占禁止法、労働法、知的財産法など、関連するあらゆる法分野の専門家がチームを組み、複雑で大規模な紛争に的確に対応します。
M&A取引の実行段階から関与し、将来の紛争リスクを徹底的に洗い出して予防策を講じるのはもちろんのこと、万が一紛争が発生した際には、訴訟、仲裁、調停といったあらゆる紛争解決手続きにおいて、依頼者を強力に代理します。
特に、M&A取引の価値評価や表明保証違反が争点となるような高度に専門的な紛争において、その豊富な経験と知識が最大限に活かされます。
公式サイト:https://www.amt-law.com/
日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」

「ひまわりほっとダイヤル」は、日本弁護士連合会(日弁連)が運営する、中小企業のための事業承継・M&Aに特化した相談窓口です。電話(0570-001-240)またはインターネットから24時間相談予約が可能で、全国の弁護士会と連携しているため、全国どこからでも利用できます。
多くの地域で初回30分間の相談が無料となっており、M&Aトラブルや事業承継に関する法的な悩みを気軽に相談できるのが大きな特徴です。この窓口を利用することで、M&Aトラブルに精通した弁護士と面談予約ができ、法的リスクや契約書のチェック、トラブル発生時の対応策など幅広い相談が可能です。
ただし、弁護士の指名はできませんので、特定の分野や実績を重視したい場合は、相談後に紹介された弁護士の経歴や実績を確認することをおすすめします。
「ひまわりほっとダイヤル」は、弁護士選びに不安のある方や、まずは無料で専門家の意見を聞いてみたい方にとって非常に有用な窓口です。全国規模で利用できるため、地方の中小企業や個人事業主にもアクセスしやすい点も強みです。
公式サイト:https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
M&Aトラブルに関する弁護士費用の詳細
M&Aトラブルについて弁護士に相談・依頼する際の費用は、案件の複雑さや規模、依頼する業務の範囲によって大きく異なります。相談料から始まり、着手金、成功報酬、契約書作成料、デューデリジェンス料など、様々な費目が発生する可能性があります。
費用体系は弁護士事務所によって異なるため、複数の事務所から見積もりを取得して比較検討することが重要です。また、単に費用の安さだけでなく、M&A案件の経験や専門性、対応の迅速さなども考慮して弁護士を選ぶべきでしょう。
費用対効果を意識しながらも、必要な法的支援は惜しまないバランス感覚が重要といえます。
| 費目 | 費用相場(目安) | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 相談料 | 5,000円~20,000円/時 | 初回または継続相談時に発生。M&A専門相談は高め。初回無料の場合もあるが、専門案件は有料が多い。 |
| 着手金 | 100万円~200万円以上 | 正式依頼時に発生。案件規模や複雑さで変動。経済的利益の2~8%程度が目安。返金不可。 |
| 成功報酬 | 経済的利益の2~20% | M&A成立時に発生。取引金額に応じて高額になることも。段階的報酬や条件設定がある場合も。 |
| 顧問契約料 | 月額3万円~10万円以上 | 継続的な法務サポート。契約書チェック等が含まれることも。特殊業務は別途料金の場合あり。 |
| 契約書作成・チェック料 | 5万円~15万円/件 | 契約書の種類・複雑さで変動。M&A特有の契約書は高額傾向。顧問契約で無料の場合も。 |
| デューデリジェンス料 | 1時間2万円~5万円 | 調査範囲・規模で変動。案件全体で数十万~数百万円。深さと費用のバランスが重要。 |
| タイムチャージ制 | 1時間3万円~5.5万円 | 実働時間に応じて課金。パートナー弁護士は高額。作業量が予測しにくい案件で採用されやすい。 |
| 実費(日当・交通費等) | 半日3~5万円/1日5~10万円 | 交通費・宿泊費・印紙代等の実費。遠方出張や訴訟時に発生。案件規模で大きく変動。 |
相談料
相談料は弁護士との初回面談や継続的な相談時に発生する基本的な費用です。M&Aに関する相談の場合、一般的な法律相談よりも専門性が高いため、費用設定も異なります。
相談料の費用相場は、1時間につき数千円から数万円程度で、平均としては1万円程度とされています。より具体的には、30分あたり5,000円~数万円が一般的な相場です。M&Aのような専門性の高い法律相談の場合は、1時間当たり5,000円~10,000円に設定されているケースが多く見られます。
一部の弁護士事務所では初回相談を無料としている場合もありますが、M&Aのような専門的な案件では無料相談を行っているケースは比較的少ない傾向にあります。例えば、いろは法律事務所では「初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別)」としていますが、「資料の精査、法的調査を要する等の相談内容によっては有料相談となる場合がある」と注記されています。
弁護士選びの際には、無料相談の有無や相談料の設定を事前に確認することで、初期コストを抑えることができるでしょう。
着手金
着手金は弁護士に業務を正式に依頼する際に支払う初期費用です。この費用は案件の成否にかかわらず返金されないため、その金額設定は重要な検討事項となります。
M&A案件における着手金は、一般的に案件の規模や複雑さによって大きく変動します。M&Aの規模に応じて100万円~200万円程度の着手金が発生することが一般的です。着手金の算定基準としては、経済的利益(M&A取引の金額)の2%~8%程度が相場とされています。
例えば、中小企業の事業承継型M&Aでは比較的小規模な着手金となる場合もありますが、複数の企業が関わる大型案件や複雑な国際M&A案件では、より高額な着手金が設定されることが一般的です。
着手金は弁護士事務所によって料金体系が異なるため、M&A案件に強い弁護士を選ぶ際には、着手金の金額だけでなく、それに含まれるサービスの範囲や内容についても確認することが重要です。また、一部の弁護士事務所では着手金をゼロとする代わりに月次報酬を設定している場合もあります。
成功報酬
成功報酬はM&A取引が成立した場合にのみ発生する費用で、弁護士の貢献度に対する対価として支払われます。この費用項目はM&A案件の結果に直結するため、最も金額が大きくなりやすい費目の一つです。
M&Aにおける成功報酬の相場は、旧日弁連基準によれば経済的利益の2~16%とされています2。より具体的には、M&Aによって得られる経済的利益の10%~20%が設定されることが多く、案件の規模によっては1,000万円以上になることもあります。
成功報酬の算定方法は、M&A取引金額に対する一定割合を基本としますが、案件の難易度や取引の複雑さによって調整されることがあります。また、段階的な成功報酬体系を採用している弁護士事務所もあり、例えば基本合意書の締結時、最終契約締結時、クロージング時など、プロセスの各段階で一部の報酬が発生する場合もあります。
弁護士を選択する際には、成功報酬の料率だけでなく、何をもって「成功」とするのか、いつ支払いが発生するのかなど、条件についても明確に確認しておくことが重要です。交渉の結果や最終的な取引条件によっては、当初の想定よりも成功報酬が高額になる可能性もあることに留意すべきでしょう。
顧問契約料
顧問契約は、継続的に法的アドバイスを受けるための契約形態で、M&Aトラブル対応を含む様々な法務サポートを受けることができます。
顧問契約料の相場は、月額3~10万円程度が一般的です。法律事務所の規模や提供されるサービスの内容によって、月額数万円から数十万円まで幅があります。例えば、月額3万円の基本プランであっても、契約書のリーガルチェックが無料で含まれていることが多いため、M&A関連の契約書を頻繁に確認する必要がある企業にとっては費用対効果が高いといえるでしょう。
顧問契約のメリットは、発生したM&Aトラブルに対して迅速に対応できることに加え、予防法務の観点からもリスクを事前に軽減できる点にあります。顧問弁護士は企業の事業内容や経営方針を理解しているため、M&A検討段階から適切なアドバイスが可能です。
ただし、顧問契約に含まれるサービスの範囲は事務所により異なるため、M&A案件の法務デューデリジェンスや大規模な契約書作成などの特殊業務は別途料金が発生する場合もあります。契約前にサービス内容と料金体系を詳細に確認することが重要です。
契約書作成・リーガルチェック料
M&A取引においては、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、合併契約書など、様々な契約書の作成や既存契約書のチェックが必要になります。これらの業務に対する費用は契約書の複雑さや規模によって変動します。
スポットでの依頼の場合、契約書作成・リーガルチェックの費用相場は5~15万円程度です。特に売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書などの典型契約は5万円程度で対応可能な場合が多いですが、取引基本契約書や業務委託契約書など事業内容の理解が必要な契約書の場合には、10~15万円程度かかることが一般的です。
M&A特有の契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など)は複雑になりやすく、表明保証条項や補償条項など専門的な条項も多いため、より高額になる傾向があります。また、契約交渉のサポートなども含む場合は追加費用が発生します。
顧問契約を結んでいる場合は、基本的な契約書のリーガルチェックは無料で受けられることも多いため、定期的に契約書の確認が必要な企業は顧問契約を結ぶことでコストを抑えられる可能性があります。契約書作成・チェックを依頼する際は、対象となる契約書の種類や量、作業の範囲を明確にして見積もりを取ることが重要です。
法務デューデリジェンス料
デューデリジェンスは、M&A取引において対象企業の法的・財務的・事業的リスクを調査する重要なプロセスです。法務デューデリジェンスを弁護士に依頼する場合の費用は、調査対象の規模や範囲によって大きく変動します。
法務デューデリジェンスの費用相場は、弁護士の場合、1時間あたり2万円~5万円が一般的です。1日の実働を7~8時間とした場合、1日あたり14万円~40万円程度かかります。案件全体としては、数十万円から数百万円程度が相場となっており、M&Aの規模が大きくなるほど費用も増加する傾向にあります。
デューデリジェンスのコストは通常「コンサルタントの単価×人数×作業日数」で計算されるため、調査項目が多い場合や対象企業の複雑性が高い場合は費用が高額になる傾向があります。例えば、複数の子会社を持つ企業グループのM&Aや、海外企業との取引では、より多くの時間と人員が必要となるため費用が増加します。
デューデリジェンスはM&A後のトラブル防止に不可欠ですが、コスト削減のために調査範囲を過度に制限すると、重要なリスクを見逃す可能性があります。調査の深さと費用のバランスを適切に取ることが重要です。
タイムチャージ制の費用
タイムチャージ制は、弁護士が業務に費やした時間に応じて料金が発生する課金方式です。M&Aトラブルのような複雑で予測が難しい案件では、このような時間制報酬を採用する事務所も増えています。
タイムチャージの費用相場は、パートナー弁護士の場合1時間当たり5万5000円(消費税込)、アソシエイト弁護士の場合1時間当たり3万3000円(消費税込)が標準的とされています。いろは法律事務所では報酬金実働部分として1時間3万円~と記載されていることからも、1時間あたり3万円~5万5000円程度が相場といえるでしょう。
タイムチャージ制のメリットは、実際の作業量に応じた公正な料金設定が可能な点です。特にM&Aトラブル解決のように、事前に作業量を見積もりにくい案件では柔軟に対応できます。一方で、費用の上限が定まらないというリスクもあります。
タイムチャージ制を採用している弁護士に依頼する場合は、月ごとの概算費用の報告を受けるなど、費用管理の方法を事前に確認しておくことが重要です。また、どのような業務がタイムチャージの対象となるのか(電話やメールのやり取りなども含むのか)についても明確にしておくべきでしょう。
実費(日当、交通費など)
弁護士費用には、基本報酬とは別に実際にかかった経費が請求される「実費」があります。M&Aトラブルの解決過程では、様々な実費が発生する可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。
実費として一般的に請求されるのは、交通費、宿泊費、印紙代、郵送費などです。また、遠方での打ち合わせや裁判所への出頭などにかかる「日当」も実費として請求されることがあり、半日3~5万円、1日5~10万円程度が相場となっています2。
特にM&A案件では、対象企業の訪問調査や、遠方での交渉、契約締結などが発生するケースが多いため、交通費や日当が高額になる可能性があります。また、M&Aトラブルが訴訟に発展した場合には、印紙代などの裁判費用も発生します。
実費は案件によって大きく変動するため、事前の見積もりが難しい費目です。そのため、依頼時に想定される実費の種類と概算について確認し、定期的に実費の使用状況について報告を受けるなど、コスト管理の仕組みを整えておくことが重要です。特に複数の弁護士が関わる大型案件では、実費が予想以上に膨らむ可能性があることを念頭に置いておく必要があります。
M&Aトラブルの紛争事例と類型
M&A取引においては、交渉開始から取引完了後の統合プロセスに至るまで様々な局面で法的紛争が生じる可能性があります。これらのトラブルの類型を把握することは、リスクを認識し、適切な対策を講じる上で重要です。
表明保証違反
M&A契約において、売り手は買手に対し、対象会社の財務状況や法務、事業に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。この表明保証に反する事実が取引後に判明した場合、買手は売り手に対して損害賠償を請求するなどの法的措置を講じることがあります。
これはM&A紛争の中でも特に頻繁に見られる類型です 。中小企業のM&Aにおいては、情報開示の不十分さや買手のデューデリジェンスの不足から、取引後に予期せぬ問題が表面化し、表明保証違反を巡る紛争に発展するケースが増加傾向にあります 。
表明保証の内容は多岐にわたり、財務諸表の適正性、簿外債務の不存在、訴訟の有無、知的財産権の状況など、多岐にわたります 。これらの表明保証が事実と異なる場合、買手は損害賠償請求を行う可能性があります 。
クロージング後の紛争
M&A取引が完了した後、買収価格の調整や買収後の事業統合に関する認識のずれから紛争が生じることがあります 。
契約条件の解釈の相違、期待されたシナジー効果が得られない、買収後に予期せぬ負債や問題が発覚するなどが原因として挙げられます 。特に、買収後の事業運営や統合プロセスにおけるコミュニケーション不足や連携不足は、紛争の温床となりやすいと考えられます。
アーンアウト紛争
買収価格の一部が、買収後の対象会社の業績に応じて支払われるアーンアウト条項が設定されている場合、業績目標の達成度合いやアーンアウト金額の算定方法を巡って紛争が生じることがあります 。
業績目標の解釈、買手の経営努力の不足、市場環境の変化などが紛争の原因となることがあります。
競業避止義務違反
M&A契約には、売り手(特に旧経営者)が一定期間、買収した事業と競合する事業を行うことを禁止する競業避止義務が定められることがあります。
売り手がこの義務に違反した場合、買手は差止請求や損害賠償請求などの法的措置を講じることがあります 。競業避止義務の範囲や期間の妥当性が争点となることもあります 。
株主間紛争
対象会社に複数の株主が存在する場合、M&Aの条件や手続き、買収後の経営方針などを巡って株主間で紛争が生じることがあります 。少数株主の権利保護や、特定の株主への有利な条件設定などが問題となることがあります。
デューデリジェンス不足に関連する問題
買収前のデューデリジェンス(Due Diligence:対象会社の詳細な調査)が不十分であった場合、取引後に予期せぬリスクや問題が発覚し、紛争の原因となることがあります 。
財務、法務、事業など多岐にわたる調査の不足は、後々のトラブルを招く可能性を高めます。M&Aにおいては、専門家による徹底的なデューデリジェンスが不可欠です 。
契約不履行
M&A契約に定められた義務が履行されない場合、契約不履行として紛争が生じることがあります 。買収代金の未払い、資産の引き渡しの遅延、クロージングに必要な手続きの遅延などが該当します。
詐欺
稀なケースではありますが、M&A取引において一方当事者が他方当事者を欺罔する行為が行われることがあります 。財務状況の虚偽表示、重要な事実の隠蔽などが該当し、重大な法的責任を問われる可能性があります。
専門家である弁護士や会計士などの関与は、このような詐欺のリスクを低減するために重要です 。
その他の新たな紛争類型
近年では、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する問題や、M&AプロセスにおけるAI技術の利用に関連する新たな紛争類型も出現しつつあります 。
企業の持続可能性や倫理的な側面に注目が集まる中で、ESGに関する情報開示の不備や誤りが紛争の火種となる可能性があります。また、AIによる評価やリスク分析の誤りが、取引後のトラブルにつながることも考えられます。
表1:M&Aトラブルの類型と法的問題
| M&Aトラブルの類型 | 概要 | 潜在的な法律リスク |
|---|---|---|
| 表明保証違反 | 売手の会社状況に関する表明保証が取引後に虚偽と判明 | 損害賠償請求、契約解除 |
| クロージング後の紛争 | 取引完了後の契約解釈や統合プロセスに関する意見の相違 | 契約不履行、特定履行請求 |
| アーンアウト紛争 | 業績連動型対価の算定や達成度合いに関する争い | 契約不履行、損害賠償請求 |
| 競業避止義務違反 | 売手が契約上の競業避止義務に反して競合事業を開始 | 差止請求、損害賠償請求 |
| 株主間紛争 | M&Aの条件や手続き、買収後の経営方針に関する株主間の対立 | 株主代表訴訟、差止請求 |
| デューデリジェンス不足に関連する問題 | 事前調査の不備により取引後に予期せぬリスクや問題が発覚 | 契約不適合責任、損害賠償請求 |
| 契約不履行 | M&A契約に定められた義務が一方当事者によって履行されない | 契約解除、損害賠償請求、特定履行請求 |
| 詐欺 | 一方当事者が他方当事者を欺罔してM&Aを成立させる | 契約取消、損害賠償請求、刑事告訴 |
| その他の新たな紛争類型 | ESG関連の情報開示不備やAI利用の誤りによる紛争 | 損害賠償請求、規制違反 |
まとめ
M&Aトラブルに強い弁護士の7つの特徴として、M&A専門の豊富な経験と実績、財務・会計の深い理解力、業界特性の把握力、卓越した交渉力とコミュニケーション能力、法的リスク管理能力、デューデリジェンスの専門性、契約書作成・レビューの卓越した能力を挙げました。
これらの特徴を持つ弁護士を選定することで、M&Aのリスクを最小化し、トラブルが発生した場合でも適切な対応が可能になります。M&Aは企業の将来を左右する重要な経営判断であり、適切な法的サポートを受けることが成功への第一歩となるでしょう。