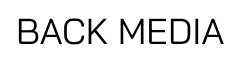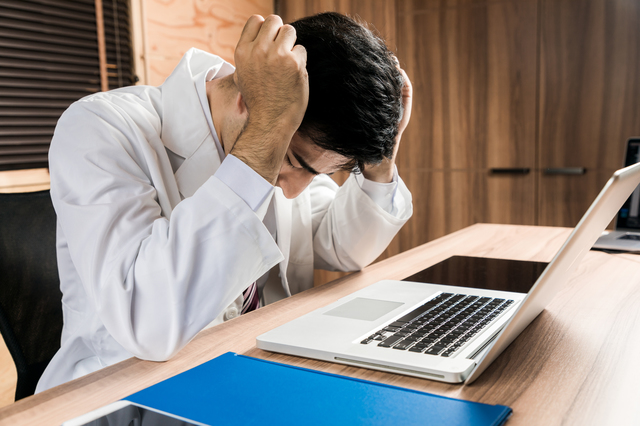本記事では医療事故・医療過誤に強い弁護士の選び方と相談のポイントを、以下3つの観点(弁護士に相談すべきタイミング、弁護士の専門性の見極め方、費用相場と対応エリア)から解説します。
- 医療事故・医療過誤とは何か、そしてその違い
- 医療過誤における弁護士の役割と解決までの流れ
- 実績ある弁護士の見つけ方と相談時の注意点
医療ミスによって身体的・精神的な被害を受けた方、またはご家族が医療機関とのトラブルに直面している方に向けて、法的に適切な対処法と信頼できる弁護士の選び方を明確に提示します。
読了後には、医療事故の被害者としてどのように権利を主張し、弁護士に何を相談すべきかの判断力が身につき、適切な法的アクションを自信を持って進められるようになります。
医療事故などの訴訟において勝訴率は約20.0%とされています。
(参照元:地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率令和5年)
| 年 | 判決 | 和解 | 請求の放棄 | 請求の認諾 | 取下 | その他 | 計 |
| 平成27年 | 282 | 387 | 2 | 3 | 32 | 81 | 787 |
| 平成28年 | 269 | 404 | 4 | 1 | 44 | 68 | 790 |
| 平成29年 | 254 | 425 | 4 | 0 | 27 | 70 | 780 |
| 平成30年 | 253 | 422 | 2 | 1 | 37 | 91 | 806 |
| 平成31年 | 253 | 475 | 4 | 0 | 47 | 74 | 853 |
| 令和元年 | 203 | 355 | 7 | 1 | 42 | 58 | 666 |
| 令和2年 | 277 | 446 | 2 | 0 | 48 | 77 | 850 |
| 令和3年 | 256 | 426 | 7 | 0 | 63 | 54 | 806 |
| 令和4年 | 276 | 416 | 1 | 0 | 33 | 38 | 764 |
医療関係の裁判は年々増えており、増えた分だけ病院も裁判にならないような対策を設けている可能性が高くなります。では、自分の大切な人が医療事故で大きな後遺症を抱えてしまった場合どのように裁判に臨んだらよいのでしょうか。
ここでは、弁護士の探し方や依頼するメリット、相談のタイミング・費用・訴訟の流れなど起訴するにあたり最低限把握しておいてほしい知識をまとめました。
医療事故・医療過誤に強い弁護士の特徴7つ
豊富な医学知識
医療訴訟に強い弁護士は、一定水準の医学知識を有しています。具体的には、バイタルサインの正常値と異常値、血液ガス分析や血液生化学検査などの基礎的な検査項目と数値、解剖生理学や生化学の基本知識、そして臨床現場でよく使用される基本薬の名前と効用などを理解しています。
これらの知識は、カルテの読解や医療行為の適切性の判断に不可欠です。また、医学書を読み解く能力も備えており、最新の医学情報を常に収集・理解することができます。このような医学知識は、患者側の主張を適切に組み立てるだけでなく、病院側の反論に対しても的確に対応するために必要不可欠です。
ただし、医師免許を持っているかどうかは必ずしも重要ではありません。むしろ、弁護士としての経験を積みながら医学知識を深めていくことが、医療訴訟を効果的に進める上で重要です。
豊富な医療訴訟経験
医療訴訟に強い弁護士は、多数の医療事故案件を扱った経験を持っています。単に「医療事件も取り扱っています」という広告だけでなく、具体的な解決事例や勝訴判決、高額和解の実績を持っていることが重要です。
経験豊富な弁護士は、医療過誤をめぐる過失論や因果関係論などの法律問題に精通し、過去の裁判例も熟知しています。また、意見書の提出タイミング、証拠調べの方法、裁判官や病院側との交渉など、さまざまな訴訟戦術を身につけています。
これらの経験と知識は、医療訴訟を有利に進める上で極めて重要です。さらに、医療訴訟の経験が豊富な弁護士は、事件の見通しを立てる能力も高く、依頼者に対して適切なアドバイスを提供することができます。
専門家ネットワークの構築
医療訴訟に強い弁護士は、豊富な協力医のネットワークを持っています。医療分野は高度に専門化されているため、各分野の権威ある専門家の知見で主張を裏付ける必要があります。協力医は、カルテや医療画像の解読、医療行為の適切性の判断、専門的な意見書の作成などで重要な役割を果たします。
ただし、単に協力医がいるだけでは不十分です。弁護士自身が医学的な基礎知識を持ち、専門家と適切にコミュニケーションを取れることが重要です。また、協力医との信頼関係を構築し、必要な時に迅速に協力を得られる体制を整えていることも、医療訴訟に強い弁護士の特徴です。
さらに、医療訴訟に特化した法律事務所では、複数の弁護士が協力して案件に取り組むことができるため、より効果的な対応が可能になります。
カルテ解読と証拠評価能力
医療訴訟に強い弁護士は、カルテや医療画像を適切に読み解く能力を持っています。カルテは医療訴訟の核心となる証拠であり、その内容を正確に理解し、問題点を見抜く能力は不可欠です。電子カルテと手書きカルテの違いを理解し、それぞれの特性に応じた解読方法を知っています。
また、カルテ開示や証拠保全の必要性を早期に判断し、適切なタイミングで実施する能力も重要です。さらに、レントゲン写真やCT、MRIなどの医療画像を読み解く基本的な知識も持ち合わせています。これらの能力により、医療行為の問題点を的確に把握し、訴訟戦略を立てることができます。
加えて、医療訴訟に強い弁護士は、カルテや医療画像以外の証拠(看護記録、検査データなど)も適切に評価し、事案の全体像を把握する能力を持っています。
医療安全・医療経営への理解
医療訴訟に強い弁護士は、単に訴訟を遂行するだけでなく、医療安全や医療経営についても深い理解を持っています。医療事故を防ぐための安全管理システムや、医療機関の経営に関する法的問題(各種契約問題、医療関係者の労務問題、医療同意の問題など)にも精通しています。
この知識は、訴訟を避けるための予防法務にも活用されます。また、医療機関側の立場や考え方を理解することで、より効果的な交渉や和解の提案が可能になります。さらに、医療制度や保険制度の仕組みについても理解があり、損害賠償額の算定や将来の治療費の見積もりなどにも適切に対応できます。
このような総合的な理解は、持続的な医療経営の実現を目指す医療機関をサポートする上でも重要です。
高度なコミュニケーション能力
医療訴訟に強い弁護士は、高度なコミュニケーション能力を持っています。まず、依頼者である患者や遺族の気持ちに寄り添い、その心情を十分に理解する能力が必要です。同時に、複雑な医学的・法的問題を依頼者に分かりやすく説明し、訴訟の見通しや戦略について納得を得る能力も重要です。
また、協力医や他の専門家とのコミュニケーションも円滑に行え、専門的な内容を正確に理解し、それを法的な主張に反映させる能力も備えています。
さらに、裁判官や相手方弁護士とのコミュニケーションも適切に行え、効果的な主張や交渉を展開できます。このような多面的なコミュニケーション能力は、医療訴訟の複雑な構造を適切に管理し、最良の結果を導き出すために不可欠です。
継続的な学習と情報発信
医療訴訟に強い弁護士は、継続的に学習を重ね、最新の医療情報や判例を常に把握しています。医学や医療技術は日々進歩しているため、常に最新の知識をアップデートする必要があります。そのため、医学書や専門誌を定期的に読み、医療関連のセミナーや研究会に積極的に参加しています。
また、弁護士会や専門家グループでの勉強会を通じて、他の弁護士との情報交換も行っています。さらに、自らの知識や経験を外部に向けて積極的に発信しています。
ウェブサイトやブログを通じて、医療事故や医療訴訟に関する詳細な情報を提供したり、セミナーの講師を務めたりすることで、社会に貢献するとともに、自身の専門性をアピールしています。
このような継続的な学習と情報発信は、医療訴訟に強い弁護士の信頼性と専門性を高める重要な要素となっています。
医療訴訟に強い弁護士の選び方と重要なポイント5つ
医療訴訟に強い弁護士を選ぶ際の重要なポイントを5つ挙げ、それぞれ解説いたします。
医療訴訟の勝訴経験
医療訴訟で勝訴した経験を持つ弁護士を選ぶことが重要です。日本全国で年間約800件の医療訴訟が提起されていますが、患者側の勝訴率は10-15%程度にとどまります。
つまり、本当の意味で勝訴判決を得られる事例はごくわずかです。示談や和解で解決した経験だけでなく、最後まで戦い抜いて勝訴判決を勝ち取った経験を持つ弁護士は、医療訴訟に対する本気度と高い専門性を有していると言えます。
ただし、1億円を請求して100万円の賠償が認められただけでは真の勝訴とは言えません。患者や遺族の無念を晴らすことができるような、実質的な勝訴判決を得た経験があるかどうかを確認することが大切です。
医学的知識と理解力
医療訴訟を扱う弁護士は、患者よりも医療事故の内容について深く理解できていることが求められます。医療事故の被害に遭った患者は、自身の経験や調査によってある程度の知識を持っています。法律相談の際に、患者よりも病気や医療行為について詳しくない弁護士は、医療訴訟を適切に扱うことは困難です。
弁護士が医学的な基礎知識を持ち、バイタルサインの正常値や異常値、基本的な検査項目や数値、解剖生理学の知識、臨床で使用される基本薬の名前と効用などを理解していることが重要です。
カルテ解読と証拠評価能力
医療訴訟において、カルテや医療画像を適切に読み解く能力は不可欠です。専門医の助けを借りずにカルテを理解できない弁護士に依頼すると、相手方からの反論や書面作成のたびに専門医に謝礼を払う必要が生じ、訴訟費用が膨らむ可能性があります。
また、カルテ開示や証拠保全の必要性を早期に判断できる能力も重要です。電子カルテと手書きカルテの違い、証拠保全手続きの適切な実施時期、重要な証拠の見極めなど、カルテ入手前の段階で適切な判断ができる弁護士を選ぶべきです。
医療専門家とのネットワーク
優秀な医療訴訟弁護士は、協力医のネットワークを持っています。医療分野は高度に専門化されているため、各分野の権威ある専門家の知見で主張を裏付ける必要があります。しかし、単に協力医がいるだけでは不十分です。
弁護士自身が医学的な基礎知識を持ち、専門家と適切にコミュニケーションを取れることが重要です。特殊な検査や特殊なカルテの意味や目的について、専門医と対等に議論できる能力が求められます。
医療訴訟への専門性と情報発信
医療訴訟に真剣に取り組んでいる弁護士や法律事務所は、ウェブサイトやブログなどを通じて、医療事件に関する詳細な情報を発信しています。単に「医療事件も取り扱っています」という広告だけでなく、具体的な事例や医療知識、法的な解説などを提供している弁護士を選ぶべきです。
また、医療事件を専門に扱う弁護士が複数在籍している法律事務所を選ぶことも重要です。医療訴訟は複雑で時間がかかるため、1人の弁護士が多数の案件を適切に処理することは困難です。チームで対応できる体制が整っているかどうかも、選択の基準となります。
医療事故・医療過誤事件の解決に強い法律事務所5つ
弁護士法人 富永愛法律事務所
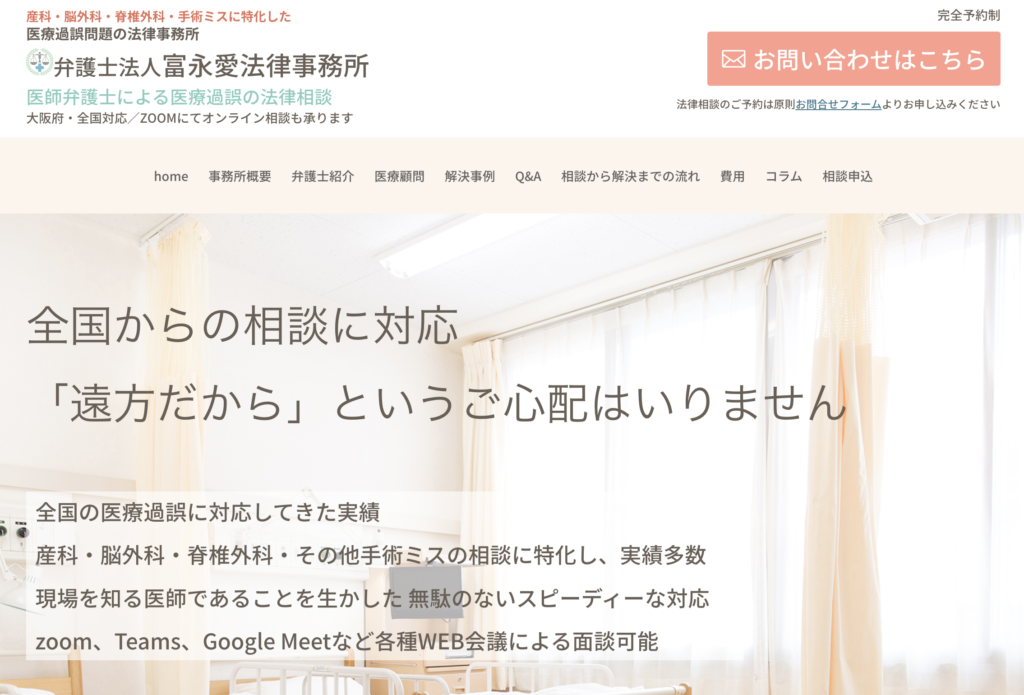
富永愛法律事務所は、現役の医師資格を持つ弁護士が運営する日本でも数少ない事務所の一つです。医師としての経験を活かし、産科や脳外科、脊椎外科など高度な専門性が必要な分野での医療過誤事件に対応しています。
カルテや医学文献の解読、専門的な意見書作成などを迅速かつ的確に行う能力が強みです。また、全国対応が可能で、遠方案件でも出張費や日当を事務所側で負担するなど、依頼者の負担軽減に配慮しています。Web会議を活用した相談も可能で、スピーディーな対応が評価されています。
公式サイト:https://www.iryou-tominagaai-law.com/
ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所は、全国76拠点を展開し、医療過誤・医療事故に特化した「医療調査・医療訴訟チーム」を擁する大規模事務所です。内科や外科、産婦人科、小児科など幅広い分野の医療事故案件に対応しており、多数の実績を持っています。
同事務所では医師や医師資格を持つ弁護士と連携しながら、医学的根拠を基にした主張立証を行います。全国対応可能である点やオンライン相談への柔軟な対応も特徴です。豊富な相談実績と体制の充実度から、多くの依頼者に支持されています。
公式サイト:https://www.vbest.jp/medical/
虎ノ門法律経済事務所

虎ノ門法律経済事務所は、所内に「医療法務部会」を設置し、医療過誤訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)に強みを持っています。同部会では定期的な勉強会や研究会を通じて知識を深めており、医療機関との交渉や示談交渉にも精通しています。また、大規模な総合病院的法律事務所として、多様な法的問題に対応できる体制を整えています。
特に持続可能な医療経営の実現をサポートするため、労務問題や契約問題にも積極的に取り組んでいます。
公式サイト:https://www.t-leo.com/corporate/medical/
大高法律事務所

大高法律事務所は、現役の医師・医学博士である弁護士が在籍しており、高度な医学知識とネットワークを活かした迅速かつ正確な対応が特徴です。最新の医学文献や海外論文も精査しながら、複雑な案件にも対応可能です。
また、初回相談料が無料(60分)であるため、気軽に相談できる点も魅力です。同事務所では死亡事故や後遺症が残る重大案件に注力しており、高い専門性が求められるケースでも信頼される存在となっています。
公式サイト:https://www.otaka-law.com/medical/
デイライト法律事務所
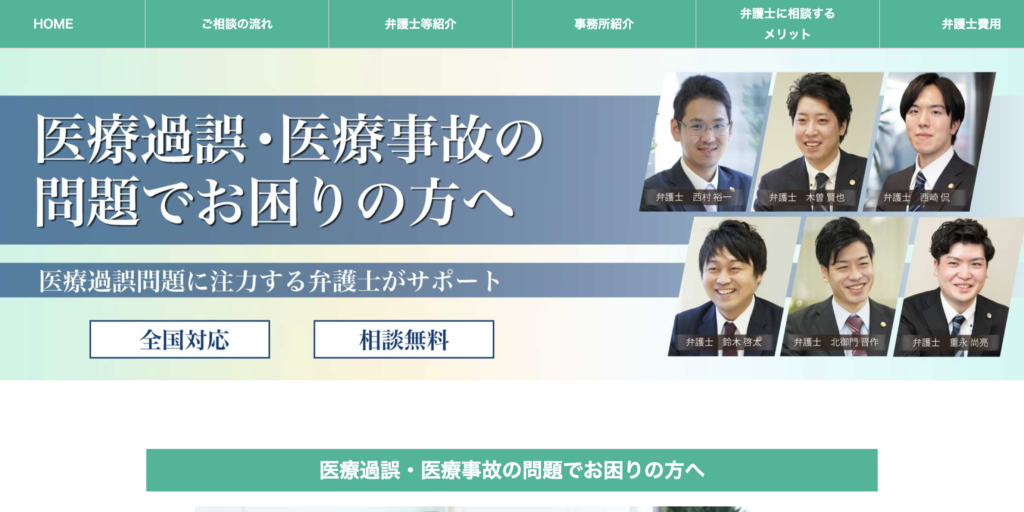
デイライト法律事務所は、「人身障害部」に所属する弁護士が医療過誤・医療事故案件に特化して対応しています。出産時の事故や手術ミスによる死亡・障害案件など、重大なケースで多くの実績があります。
カルテ取得から医学文献調査、責任追及まで一貫して行い、高度な法的主張と医学的根拠を組み合わせたアプローチが特徴です。また、ご来所だけでなくオンライン相談も可能であり、依頼者の利便性にも配慮しています。
公式サイト:https://www.daylight-law.jp/medical/
これら5つの法律事務所は、それぞれ異なる強みと専門性を持ち合わせています。依頼者としては、自身のケースに最も適した専門性と体制を持つ事務所を選ぶことが重要です。
医療訴訟に関して弁護士に依頼して病院を訴えるときの流れ
ではどのような流れで医療訴訟(病院を訴える)を行うのかまとめました。
訴訟をするための準備の流れ
証拠の保全
病院をすぐにでも訴えたいと思うかもしれませんが、まず訴訟を起こすなどのことは一切言わず、証拠となるカルテやレントゲンなどの診療記録を開示請求します。
この時、医療訴訟をするなどと言ってしまうと、病院側が身構え最悪の場合、カルテの改ざんや、診療記録の破棄をされてしまう可能性があります。
過失調査
医療過誤として損害賠償を請求するためには、病院側の過失や過失と損害との因果関係を立証する必要があります。そのため、カルテや診察記録から過失の有無や因果関係の有無を詳細に調査をすることが不可欠です。
またこの調査の結果、因果関係が認められなかった、法的責任追及が困難となった場合には、相手側の医療機関に診察内容などの説明会の開催を求めることがあります。
示談交渉
病院側の過失が認められた場合、基本的に示談交渉になります。
実際に訴訟を行う
示談が成立しなかった場合、裁判で争うことになります。最初に記載しましたが、医療事故などの医療問題において勝訴率は20%です。なので、証拠に不安が多い場合等には示談金での解決や、裁判中の和解も検討しなければいけません。
医療訴訟の流れ
ここからは裁判の流れを紹介します。分かりやすく図にまとめました。
提訴
「訴状」というものを裁判所に提出します。訴状には大きく分けて2つのことを記述します。
- 請求の趣旨:損害賠償の金額を書きます。また民事裁判で金銭賠償以外の後遺症の治療や謝罪を求めることはできません。
- 請求の原因:過失(病院側が起こしたミスの内容)・被害の内容・損害(後遺症などで発生した被害を金銭で換算したもの)・因果関係(ミスと損害との関係性)を明確に記述します。
争点整理
証拠となる書類を提出し、原告と被告の言い分の食い違いを整理します。食い違いが裁判での争点になるので、それを明確にすることが目的です。
また裁判中に言い分が一致していない点について、被害者の遺族や原告・被告の協力医が証言する場合があります。これを「尋問」といい、言い分が一致している場合には行われません。
和解
裁判の途中で、裁判所が間に立ち、話し合いが行われることがあり、合意に至れば「和解」が成立します。和解にするメリットは、判決では得られない謝罪を得られる、また全面敗訴を避けることができることです。
判決
和解に至らなかった場合に判決に至ります。医療関係の裁判にかかる期間は平均約25.1ヶ月です。(参照元:医事関係訴訟事件の件数および平均審理期間)長期線になりますが、慌てず確実に裁判に臨みましょう。
医療訴訟に強い弁護士にかかる費用は?
金額は一般的な目安であり、事案の複雑さや弁護士事務所によって異なります。「完全成功報酬型」など、異なる料金体系を採用している事務所もあるため、契約前に詳細な見積りと説明を受けることが重要です。
| 費用項目 | 概要 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 初回相談時の費用。多くの事務所で初回無料の場合あり | 30分あたり5,500円程度 |
| 調査費用 | 医療過誤の可能性を確認するための費用。カルテ精査や専門医への意見聴取など | 11万円~44万円程度 |
| 着手金 | 弁護士が案件を正式に受任した際の初期費用 | 示談交渉:22万円程度~ 調停・ADR:44万円程度~ 訴訟提起:55万円程度~ |
| 報酬金 | 案件成功時の成果報酬。獲得賠償額の一定割合 | 獲得賠償額の11%~33%程度 |
| 実費 | 案件処理中に実際に発生する経費 | 裁判の場合、50~60万円程度 |
| 日当 | 弁護士が遠隔地で活動する際の費用 | 1回あたり15,000円程度~ |
法律相談料
法律相談料は、弁護士に初めて相談する際に発生する費用です。一般的には30分あたり5,500円程度が相場ですが、事務所によっては無料相談を提供している場合もあります。医療訴訟は複雑なケースが多いため、相談時間が1時間以上に及ぶことも珍しくありません。
相談内容としては、医療事故の概要説明やカルテの確認、弁護士からの初期的なアドバイスなどが含まれます。この段階で、弁護士が事案を受任するかどうかの判断を行う場合もあります。また、相談料が無料の場合でも、具体的な調査やカルテ精査が必要になる場合には別途費用が発生することがあります。
そのため、事前に料金体系を確認し、必要な資料(カルテや診断書など)を準備しておくことが重要です。
調査費用
調査費用は、医療過誤の可能性を確認するために必要な費用です。これにはカルテや診療記録の精査、専門医への意見聴取、医学的な問題点の整理などが含まれます。調査費用は11万円から44万円程度が一般的ですが、事案の複雑さや必要となる専門家の数によって変動します。
例えば、高度な専門性を要する分野(脳外科や心臓外科など)の場合には、協力医への謝礼金が高額になることがあります。また、調査結果によって訴訟提起の可否が決まるため、この段階で慎重な判断が求められます。
一部の弁護士事務所では、この調査費用を着手金に含む場合もありますが、多くの場合は別途請求されます。依頼者としては、この費用がどのように使われるのかを明確に説明してもらうことが重要です。
着手金
着手金とは、弁護士が案件を正式に受任した際に支払う初期費用です。これは成功・不成功に関わらず返金されない性質のものです。医療訴訟の場合、示談交渉では22万円程度から、調停やADR(裁判外紛争解決手続き)では44万円程度から、訴訟提起では55万円程度からとされています。
ただし、この金額は事務所ごとに異なるほか、事件の規模や難易度によって変動します。例えば、大規模な病院を相手取るケースや、多数の証拠収集が必要なケースでは、高額になる傾向があります。
また、一部の法律事務所では「完全成功報酬型」を採用しており、この場合は着手金が不要ですが、その分報酬金が高く設定されることがあります。依頼前に契約内容を十分確認し、自分の予算と相談することが大切です。
報酬金
報酬金とは、案件が成功した場合に支払う成果報酬です。これは獲得した賠償額(和解金・判決による賠償金)の一定割合として計算されることが一般的です。通常は賠償額の11%から33%程度ですが、高額賠償の場合には割合が低く設定される場合もあります。
たとえば、1,000万円の賠償を得た場合、報酬金は110万円から330万円程度となります。この割合は事務所ごとに異なるため契約時に確認する必要があります。また、一部では固定額として設定される場合もあります。
報酬金には成功報酬としての性質があるため、高い成果を上げた弁護士ほど高額になる傾向があります。ただし、高額な報酬金設定の場合でも、その弁護士の実績や信頼性を考慮して選ぶことが重要です。
実費
実費とは、案件処理中に実際に発生する経費であり、依頼者が負担するものです。これには以下のような項目が含まれます:
- 証拠保全申立て時の収入印紙代・郵券代
- カルテや診療記録などのコピー代
- 医療画像(レントゲン写真やMRI)の現像代
- 専門医への謝礼金や交通費
医療訴訟の場合、特に証拠保全手続きや専門家意見書作成時に多額の実費が発生することがあります。また裁判所への提出資料準備にも経費がかかります。
これらは通常50~60万円程度ですが、大規模な案件ではさらに高額になる可能性があります。弁護士との契約時には実費についても明確な説明を受け、不明点を確認しておくことが重要です。
日当
日当は弁護士が遠隔地で活動する際に発生する費用であり、多くの場合1回あたり15,000円程度から設定されています。この費用には移動時間や滞在時間中の弁護士業務への対価も含まれます。たとえば裁判所への出廷や証拠保全手続きで遠方へ出張する際などに発生します。
また、大都市圏以外で活動する弁護士の場合でも、自宅または事務所から裁判所まで長時間移動するケースでは日当を請求されることがあります。ただし、大都市圏内で近距離移動の場合には日当を請求しない事務所もあります。この項目についても契約時に条件を確認しておくことで、不意な出費を避けられます。
これらすべてについて事前に詳細な見積りを提示してもらい、不明点について十分説明を受けた上で契約することが重要です。また、「完全成功報酬型」など柔軟な料金体系を提供している事務所もあるため、自分のニーズと予算に合った弁護士選びを行うよう心掛けてください。
医療事故・医療過誤に強い弁護士を探せるおすすめのポータルサイト
医療事故・医療過誤の問題は、医学的な専門知識と法律知識の両方が高度に要求される分野です。
弁護士を選ぶ際には、単に「医療分野に詳しい」というだけでなく、実際に医療過誤訴訟の経験が豊富か、勝訴実績があるか、医学的な知見を持つスタッフ(医師や看護師資格を持つパラリーガルなど)と連携しているかといった点を重点的に確認することをおすすめします。
弁護士ドットコム
弁護士ドットコムは、全国の弁護士を専門分野や所在地で検索できる日本最大級の法律ポータルサイトです。
医療事故・医療過誤に強い弁護士を探したい場合、検索機能で「医療過誤」「医療事故」などのキーワードを入力するだけで、関連する事件を多く扱っている弁護士や法律事務所のプロフィール、実績、口コミなどを簡単に確認できます。弁護士ごとに得意分野や対応可能な案件が明記されており、患者側の立場で依頼したい場合でも安心して選択できるのが特徴です。
サイト上から直接メッセージを送って相談予約が可能で、初回無料相談やオンライン面談に対応している弁護士も多く、利便性が高い点も魅力です。医療事故は専門性が求められる分野のため、弁護士ドットコムの豊富な情報量と口コミ評価を活用することで、依頼者にとって最適な弁護士選びがしやすくなっています。
ココナラ法律相談
ココナラ法律相談は、医療事故・医療過誤など幅広い法律相談に対応できる弁護士が多数登録しているサービスです。
全国の都市圏だけでなく地方都市の弁護士も網羅しており、医療事故の慰謝料請求・訴訟、説明義務違反、手術ミスなど、専門性の高い分野にも強い弁護士を検索できます。プロフィールや実績、弁護士費用、強みなどが詳細に記載されており、依頼者目線で比較検討しやすいのが特徴です。
相談は電話やオンラインで気軽に申し込みができ、初回無料相談に対応している弁護士も多く、費用面やスケジュール面での負担も少なく済みます。
また、夜間や土日祝の相談にも対応している弁護士がいるため、忙しい方や急ぎの案件にも便利です。医療事故は専門知識が不可欠なため、ココナラ法律相談で実績や専門性を重視しつつ、複数の弁護士に相談することで、より最適なサポートを受けられます。
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的な理由で弁護士費用の負担が難しい方に法律扶助を提供する公的機関です。医療事故・医療過誤に関する相談も受け付けており、まずは相談カードを作成し、法テラス東京など最寄りの窓口へ郵送することで面談日時の調整が行われます。
相談は原則1回60分で、資力要件を満たすことが条件となります。法テラスを利用した場合、弁護士費用や鑑定費用などは法テラスが立て替えてくれるため、経済的負担が大きく軽減される点が大きなメリットです。ただし、医療過誤事件は専門性や調査の重要性が高く、法テラスの報酬基準が低いために受任を断る弁護士も多いという現実もあります。
また、調査受任や複数弁護士体制には対応しにくい側面もありますが、生活保護受給者や低所得者にとっては非常に有益な制度です。法テラスは、無料または低額で法律相談や弁護士依頼を検討したい方におすすめの選択肢です。
医療訴訟を行う場合どの段階で弁護士に相談すべきか?
結論から言うと、弁護士にはできるだけ早く相談しましょう。では、何故早い方がいいのか紹介します。
医療ミスではないかと疑いが生じた段階
治療結果に納得がいかない、説明が不十分だと感じるなど、医療機関に対して不信感を抱いた時点で、まずは専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。
この段階で相談することで、そもそも法的に問題があるのか、医療訴訟として争う余地があるのかといった点について、初期の段階で専門的なアドバイスを受けることができます。
証拠収集の段階
医療訴訟を進めるためには、カルテなどの診療記録や検査結果といった証拠が不可欠です。
弁護士に相談することで、どのような証拠が必要か、どのように収集すればよいかについて具体的なアドバイスを受けることができます。場合によっては、弁護士が代理人として証拠収集を行うことも可能です。
医療機関との交渉前または交渉中の段階
ご自身で医療機関と交渉(話し合い)を試みる場合でも、事前に弁護士に相談しておくことで、交渉の進め方や注意点についてアドバイスを受けることができます。
交渉がうまくいかない場合や、医療機関側の対応に納得できない場合にも、弁護士に介入を依頼することを検討しましょう。
その他
精神的に大きな負担を感じている場合: 医療訴訟は、精神的にも時間的にも大きな負担を伴うことがあります。弁護士に依頼することで、法的な手続きを一任でき、精神的な負担を軽減できる可能性があります。
時効が迫っている場合: 医療訴訟には時効があります。不法行為に基づく損害賠償請求の場合は損害および加害者を知った時から5年、または不法行為の時(医療ミスが発生した時)から20年のいずれか早い方で時効が成立してしまいます。
医療訴訟の裁判例
核黄疸による新生児の脳性麻痺発症に関する注意義務違反事例
本件は、新生児が核黄疸を発症し、その結果として重度の脳性麻痺に至った事案です。原告(新生児とその両親)は、担当医師が核黄疸のリスクを予見し、適切な診断と治療を行うべき注意義務を怠ったとして損害賠償請求を提起しました。
新生児は出生後に黄疸が出現し、医師は光線療法を実施しましたが、血清ビリルビン値の測定や交換輸血を行わず、核黄疸の進行を防げませんでした。その結果、新生児はアテトーゼ型脳性麻痺となり、重度の運動障害や言語障害が残りました。
裁判所は、医師が血清ビリルビン値の測定や交換輸血を行える医療機関への転送を怠った点で注意義務違反があったと認定しました。また、核黄疸による脳性麻痺との因果関係も認められました。最終的に裁判所は原告側に損害賠償として約1億3,230万円を認容しました。この判例は、新生児医療における迅速かつ適切な対応の重要性を示すものです。
- 裁判所: 東京地方裁判所八王子支部
- 年月日: 平成6年11月15日
- 判決: 原告側に損害賠償として約1億3,230万円を認容
胃がん誤診による幽門側胃切除術実施事例
本件は、患者が胃がんと誤診され、不要な幽門側胃切除術を受けた事案です。患者は嘔吐や下痢の症状を訴えて病院を受診し、内視鏡検査で採取された検体が病理医によって「印環細胞がん」と診断されました。
その結果、患者は胃の3分の2を摘出する手術を受けました。しかし、摘出された胃の病理組織検査ではがん細胞は発見されず、マクロファージ(白血球の一種)の集簇であることが判明しました。
患者側は、この誤診により不要な手術を受けたとして、病理医および手術を行った大学病院に対して損害賠償請求を提起しました。裁判では、病理医による注意義務違反(善管注意義務違反)が認められました。一方で、大学病院については、再度の生検や標本取り寄せ義務までは認められないとして過失責任は否定されました。患者は訴訟係属中に死亡し、その相続人が訴訟を承継しました。
- 裁判所名: 熊本地方裁判所
- 年月日: 2025年1月24日
- 判決: 病理医の過失(注意義務違反)を認定。大学病院には過失責任なしとして患者側の請求棄却
抗凝固薬休薬期間中の脳梗塞死亡事例
本件は、62歳男性患者が大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術を受ける際、抗凝固薬リバーロキサバンの休薬期間が不適切に長く設定されたことにより、脳梗塞を発症し死亡した事案です。
手術担当医は、術前1週間の休薬を指示しましたが、これは当時の医学的知見やガイドラインに照らして過剰なものでした。手術翌日、患者は脳梗塞を発症し、その日のうちに死亡しました。
裁判所は、医師が休薬期間を1週間としたことについて過失を認めました。また、適切な休薬期間(48~78時間)であれば患者が死亡せず生存していた可能性が相当程度あったと判断し、慰謝料900万円を認定しました。ただし、因果関係については「高度の蓋然性」までは認められず、一部請求が認容されました。この判例は、抗凝固薬管理の慎重さとガイドライン遵守の重要性を示しています。
- 裁判所名: 東京地方裁判所
- 年月日: 2024年11月19日
- 判決: 医師の過失を認定し、一部請求認容(慰謝料900万円)
メディカルオンライン|抗凝固薬の休薬期間中に患者が脳梗塞で死亡したことに関して処方医の過失が認められた事例
まとめ
医療訴訟に強い弁護士を選ぶ際のポイントをまとめると、以下の特徴が挙げられます。
- 豊富な医学知識:ルテや医療記録を正確に理解し、医療行為の適切性を判断するための基礎的な医学知識を有していること。
- 医療訴訟の経験:去に多くの医療事故案件を扱った実績があり、裁判例や訴訟戦術に精通していること。
- 専門家ネットワークの構築:力医などの専門家との連携体制を持ち、専門的な意見書の作成や証拠収集を円滑に行えること。
- カルテ解読と証拠評価能力:ルテや医療画像を適切に読み解き、証拠としての価値を的確に評価できること。
- 医療安全・医療経営への理解:療機関の安全管理体制や経営に関する法的問題にも精通し、総合的な視点でアドバイスができること。
- 高度なコミュニケーション能力:頼者や専門家、裁判官などとの効果的なコミュニケーションを通じて、主張や交渉を適切に行えること。
- 継続的な学習と情報発信:新の医療情報や判例を常に学び、自身の知識や経験を積極的に発信していること。 れらの特徴を持つ弁護士を選ぶことで、医療訴訟を有利に進めることが可能となります。
これらの内容を踏まえて、最適な弁護士を選んでいただければと思います。