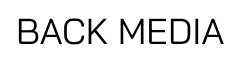著作権侵害の違反事例と損害賠償の請求額
それぞれの著作権侵害事例について詳細を解説します。

漫画村事件
漫画村は2016年から2018年にかけて運営された、日本最大の海賊版サイトでした。運営者の星野ロミは、著作権者の許可なく多数の漫画をスキャンしてウェブサイトにアップロードし、無料で閲覧できるようにしました。
サイトは広告収入で運営され、最盛期には月間アクセス数が1億6000万回を超え、推定被害額は3000億円以上に上りました。出版社や漫画家から強い批判を受け、著作権侵害の象徴的な事例となりました。
2019年7月、星野ロミがフィリピンで逮捕され、日本に身柄が移送されました。2021年6月、東京地裁は星野に対し、著作権法違反の罪で懲役3年、罰金1000万円の実刑判決を言い渡しました。
この事件を機に、日本政府は海賊版サイト対策を強化し、ブロッキング(接続遮断)の是非についても議論が行われました。また、正規の電子書籍サービスの普及促進や、著作権教育の重要性が再認識されることとなりました。
理容室BGM訴訟
2011年、札幌市の理容室「はるとも」が店内BGMとして音楽を無断再生していたことが問題となりました。日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権侵害を主張し、訴訟を起こしました。
この事件の焦点は、店舗での音楽の再生が著作権法上の「演奏」に当たるかどうかでした。理容室側は、BGMは営利目的ではなく、著作権法の「非営利目的の演奏」に該当すると主張しました。
しかし、2012年8月、札幌地裁は理容室でのBGM再生を「顧客誘引のための手段」と判断し、著作権侵害を認定しました。裁判所は音楽使用の差し止めと約24万円の損害賠償を命じました。
この判決は、小規模店舗でのBGM使用にも著作権使用料が必要であることを明確にし、多くの店舗経営者に影響を与えました。JASRACは判決後、理容室や美容室向けの包括的な音楽利用許諾制度を導入し、著作権管理の適正化を図りました。
フラダンス振付訴訟
2013年、フラダンス教室を運営する会社が、他者の振付を無断で使用したことが問題となりました。振付師のケウラ・カウアイ・チングさんが著作権侵害を主張し、訴訟を起こしました。
この事件の焦点は、フラダンスの振付が著作権法で保護される「著作物」に該当するかどうかでした。被告側は、フラダンスの振付は伝統的な動きの組み合わせに過ぎず、著作物性がないと主張しました。
しかし、2015年2月、東京地裁は振付に創作性を認め、著作物性を認定しました。裁判所は該当の振付の指導停止と約100万円の損害賠償を命じました。
この判決は、ダンスの振付も著作権法で保護される可能性があることを示し、ダンス業界に大きな影響を与えました。振付師の権利保護が進む一方で、伝統芸能の継承や発展との兼ね合いについても議論が起こりました。
無許諾グッズ販売事件
2020年、「鬼滅の刃」などの人気アニメキャラクターの無許諾グッズを販売・所持していた事例が発生しました。東京都内の雑貨店経営者が、著作権者の許可なくキャラクターグッズを製造・販売していたことが発覚しました。
警視庁は、著作権法違反の疑いで雑貨店経営者を逮捕しました。押収されたグッズは約1万点に上り、その販売額は約1000万円に達していたとされています。
この事件は、人気コンテンツの二次創作物や非公式グッズの問題を浮き彫りにしました。著作権者の許可なく商品化する行為が違法であることが改めて認識され、同様の事例の抑止力となりました。
また、この事件を機に、正規ライセンス商品の重要性や、ファンアートなどの二次創作と商業利用の線引きについても議論が活発化しました。
参照:鬼滅の刃」無許諾グッズを販売・所持、著作権法違反で摘発 | 著作権侵害事件 | ACCS
アニメ制作資料無断コピー販売
2019年、アニメ制作の資料集を無断でコピーして販売したグループの事件が発覚しました。このグループは、アニメ制作会社から流出した原画や設定資料などをコピーし、オークションサイトなどで販売していました。
警視庁は著作権法違反の疑いでグループのメンバー3人を逮捕しました。押収された資料は約10万点に上り、その販売額は約2億円に達していたとされています。
この事件は、アニメ制作現場のセキュリティ問題や、貴重な制作資料の流出リスクを浮き彫りにしました。また、ファンの間で人気の高いアニメ制作資料の取り扱いについて、業界全体で再考する契機となりました。
事件後、多くのアニメ制作会社が資料管理の厳格化や、正規のアートブック発売などの対策を講じました。同時に、ファンの収集欲求と著作権保護のバランスをどう取るかという課題も浮上しました。
参照:アニメ制作資料集の無断コピー品を販売、グループを摘発 | 著作権侵害事件 | ACCS
投資情報ブログ無断転載
2018年、投資情報提供会社が他社のブログ記事を無断転載した事例が問題となりました。被害を受けた会社が著作権侵害を主張し、訴訟を起こしました。
この事件の焦点は、ウェブ上の記事の著作権保護と、情報の引用や転載の境界線でした。被告側は、投資情報は事実の伝達に過ぎず、著作物性がないと主張しました。
しかし、裁判所は記事の選択や構成に創作性を認め、著作権侵害を認定しました。被告に対し、約100万円の損害賠償支払いが命じられました。
この判決は、ウェブ上のコンテンツも著作権法で保護されることを改めて示し、安易な記事の転載や引用に警鐘を鳴らしました。同時に、情報の共有と著作権保護のバランスについて、デジタル時代における新たな課題を提起しました。
参照:裁判所|平成26年(ワ)第30442号 損害賠償請求事件
旅行写真無断使用
2017年、旅行業者が職業写真家のハワイの写真を無断で自社ブログに掲載した事例が発生しました。写真家が著作権侵害を主張し、訴訟を起こしました。
この事件の焦点は、インターネット上で公開されている写真の使用と著作権の関係でした。被告側は、ウェブ上の画像は自由に使用できると誤解していたと主張しました。裁判所は写真の著作物性を認め、著作権侵害を認定しました。被告に対し、約15万円の損害賠償支払いが命じられました。
この判決は、インターネット上の画像も著作権で保護されることを改めて示し、安易な画像の無断使用に警鐘を鳴らしました。また、企業のウェブマーケティングにおける著作権意識の向上にも寄与しました。
参照:平成23年(ワ)第32584号 損害賠償等請求事件
ニュース見出し無断転載
2016年、デジタルコンテンツ会社が新聞社のニュース見出しを無断転載した事例が問題となりました。新聞社が著作権侵害を主張し、訴訟を起こしました。
この事件の焦点は、ニュース見出しの著作物性と、ニュースアグリゲーションサービスの在り方でした。被告側は、見出しは事実の簡潔な表現に過ぎず、著作物性がないと主張しました。
しかし、裁判所は見出しの選択や表現に創作性を認め、著作権侵害を認定しました。被告に対し、約24万円の損害賠償支払いが命じられました。
この判決は、短い文章でも著作権で保護される可能性があることを示し、ニュースキュレーションサービスの在り方に一石を投じました。同時に、情報の自由な流通と著作権保護のバランスについて、新たな議論を喚起しました。
SNSアイコン無断使用
近年、タレントやマンガキャラクターの画像を無断でSNSのアイコンとして使用する行為が問題視されています。これは、他者の著作物を許可なく使用する点で著作権侵害に当たる可能性があります。
具体的な罰則は事例によって異なりますが、著作権法違反として罰せられる可能性があります。著作権法では、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
この問題は、SNSの普及に伴い顕在化してきました。多くのユーザーが著作権の知識不足から無自覚に侵害行為を行っているケースが多いとされています。
著作権者側も、ファンの表現行為を過度に制限したくないというジレンマを抱えています。そのため、明確な法的措置よりも、啓発活動や注意喚起が主な対応となっています。
テレビ番組の無断配信
テレビ番組を許可なくインターネット上で配信する行為は、深刻な著作権侵害問題となっています。特に、ライブストリーミングサービスを利用した無断配信が増加しています。
この行為は、著作権者の許可なく作品を公開する点で著作権法違反に該当します。罰則としては、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
実際に2020年には、人気アニメをライブストリーミングサービスで無断配信していた男性が逮捕されるなど、取り締まりが強化されています。
この問題は、テレビ番組の視聴形態の変化や、インターネットの普及に伴う著作権意識の希薄化が背景にあると指摘されています。放送局や権利者団体は、正規の配信サービスの充実や、著作権教育の強化などの対策を進めています。
SNSからキャラ弁まで、我々の身近にある著作権侵害の事例5つ
SNSでのキャラクター画像の無断使用
SNSのプロフィール画像やアイコンとして、人気アニメやマンガのキャラクター画像を無断で使用することは、著作権侵害に該当します。これは、著作権者の許可なく著作物を公衆に送信する行為であり、公衆送信権の侵害となります。
多くのユーザーが気軽に行っている行為ですが、法的には問題があります。特に注意が必要なのは、個人的な使用(例えば、自分の携帯電話の待ち受け画面)であれば私的使用として許容されますが、SNSのように不特定多数の人が閲覧できる場所での使用は著作権侵害となる点です。
著作権者によっては、ファンの表現行為として黙認するケースもありますが、正式な許可なく使用することはリスクを伴います。安全な方法としては、自分で描いたイラストや著作権フリーの画像を使用することが推奨されます。
動画配信での音楽の無断使用
YouTubeなどの動画配信サイトで、BGMとして市販の音楽を無断で使用することも著作権侵害に該当します。これは、著作権者の許可なく音楽を複製し、公衆に送信する行為であり、複製権および公衆送信権の侵害となります。
多くの動画クリエイターが陥りやすい問題ですが、たとえ数秒間の使用であっても、原則として著作権侵害となります。YouTubeなどのプラットフォームは、著作権侵害コンテンツを検出するシステムを導入しており、違反が見つかると動画が削除されたり、アカウントが停止されたりする可能性があります。
合法的に音楽を使用するには、著作権フリーの音楽を利用するか、著作権管理団体(例:JASRAC)から許諾を得る必要があります。また、YouTubeが提供する著作権フリーの音楽ライブラリを利用するのも一つの方法です。
ブログでの他人の写真や記事の無断転載
個人ブログやウェブサイトで、他人が撮影した写真や書いた記事を無断で転載することも著作権侵害に該当します。これは、著作権者の許可なく著作物を複製し、公衆に送信する行為であり、複製権および公衆送信権の侵害となります。
インターネット上に公開されている情報は自由に使えると誤解している人も多いですが、ウェブ上の文章や画像にも著作権が存在します。特に、プロの写真家や記者が作成したコンテンツを無断で使用すると、深刻な問題に発展する可能性があります。
ただし、引用の要件を満たす場合は、著作権者の許可なく著作物を利用することができます。引用の要件には、出典の明示、引用部分の明確な区別、引用の必然性などがあります。安全に他人の著作物を利用するには、著作権者から許可を得るか、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなどのオープンライセンスが付与された著作物を利用することが推奨されます。
海賊版サイトからの漫画のダウンロード
いわゆる「海賊版サイト」から、違法にアップロードされた漫画をダウンロードする行為も著作権侵害に該当します。これは、著作権者の許可なく著作物を複製する行為であり、複製権の侵害となります。
2021年1月から、違法にアップロードされたものと知りながら漫画をダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法となり、刑事罰の対象にもなりました。
ただし、
- 軽微なもの(漫画の一コマ~数コマだけ等)
- 二次創作・パロディ等の二次的著作物(翻訳を除く)
- 著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
は、規制対象外とされています。海賊版サイトの利用は、著作権者に大きな経済的損失を与えるだけでなく、ユーザー自身もウイルス感染などのリスクにさらされる可能性があります。合法的に漫画を楽しむには、正規の電子書籍サービスや公式アプリを利用することが推奨されます。
キャラクター弁当(キャラ弁)の写真のSNS投稿
人気キャラクターを模したお弁当(キャラ弁)を作り、その写真をSNSに投稿する行為も、場合によっては著作権侵害に該当する可能性があります。これは、著作権で保護されたキャラクターを複製し、その写真を公衆に送信する行為であり、複製権および公衆送信権の侵害となる可能性があります。
キャラ弁自体を作ることは、通常は私的使用の範囲内として問題ありません。しかし、その写真をSNSにアップロードすると、たとえ販売目的がなくても、公衆送信権侵害となる可能性があります[5]。
ただし、実際にはインターネット上で多数のキャラ弁写真が投稿されており、多くの場合、キャラクターの著作権者によって黙認されているのが現状です。それでも、商業目的での使用や、著作権者のイメージを損なうような使用は避けるべきです。また、キャラクターの特徴を抽象化し、オリジナルのアレンジを加えることで、著作権侵害のリスクを低減できる可能性があります。
著作権侵害の成立要件
著作権侵害が成立する要件については、下記の5つを全て満たす必要があります。
著作物性があること
著作権侵害が成立するためには、まず侵害の対象となる作品が著作物であることが必要です。著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています[1]。
著作物性の判断基準として重要なのは「創作性」です。ここでいう創作性とは、作者の個性が表れていることを意味し、高度な芸術性や新規性までは要求されません。例えば、素人が描いたイラストや、日記のような個人的な文章にも創作性は認められます[2]。
一方で、
- 単なる事実やデータ(例:「東京タワーの高さは333m」)
- ありふれた表現(例:「いつもお世話になっております」といったあいさつ)
- 短文で自由度の低すぎる表現(例:「今でしょ」のようなキャッチフレーズ)
などには、通常、著作物性は認められません。
また、著作権法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないとしています。同様に、プログラミング言語や規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)も著作物には該当しません[2]。
著作物性の判断は時に難しく、裁判でも争点となることがあります。特に、いわゆる応用美術(実用品のデザインなど)の著作物性が問題となることが多いです。このような場合、その表現が通常のデザインプロセスを超えて、美的創作性を有するかどうかが判断基準となります。
著作権が存続していること
著作権侵害が成立するためには、対象となる著作物に著作権が存続していることも必要です。著作権には存続期間が定められており、この期間を過ぎると著作権は消滅し、誰でも自由に利用できるパブリックドメインとなります[2]。
日本の著作権法では、原則として著作者の死後70年を経過するまで著作権が存続します。ただし、著作者の死亡時期が不明な場合や、法人著作の場合など、いくつかの例外規定があります。
例えば、著作者の死亡時期が不明な場合は、公表後70年を経過するまで著作権が存続します。また、法人著作の場合は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)を経過するまで著作権が存続します。
映画の著作物については、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)を経過するまで著作権が存続します。
また、戦時加算という特殊な規定もあります。これは、第二次世界大戦の影響で著作権の適切な保護が行われなかった期間を補償するもので、連合国の著作物については一定期間が加算されます。
著作権の存続期間は国際的な取り決めによって各国で調和が図られていますが、国によって若干の違いがあります。そのため、海外の著作物を利用する際は注意が必要です。
なお、著作権が消滅した著作物であっても、それを翻訳や翻案した二次的著作物には新たに著作権が発生することに注意が必要です。例えば、シェイクスピアの作品は著作権が消滅していますが、その現代語訳には訳者の著作権が存在します。
依拠性があること
著作権侵害が成立するためには、侵害が疑われる著作物が既存の著作物に依拠して作成されたことが必要です。これを「依拠性」と呼びます。
依拠性とは、既存の著作物を参考にしたり、それをもとに創作したりしたことを意味します。例えば、他人の小説を読んでそのストーリーを真似して小説を書いたり、他人の絵画を見てそれを模写したりする場合には、依拠性が認められます。
一方で、既存の著作物を全く知らずに、偶然似たような著作物を独自に創作した場合には、依拼性がないため著作権侵害は成立しません。最高裁判所の判決(昭和53年9月7日)でも、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」とされています[5]。
依拠性の立証は難しい場合があります。特に、侵害者が依拠を否認する場合、著作権者側で依拠の事実を直接証明することは困難です。そのため、裁判では間接事実から依拠性を推認することが多くなります。
具体的には、①両著作物の類似性、②原告著作物へのアクセスの機会の存在、という2点から依拠性が推認されることがあります。例えば、ある裁判例では、被告が原告の著作物を所持し、これに目を通したり参照したりしたこと、両著作物間に表現上全く同一のものや、わずかに改めただけのものが複数見られること、被告の著作物に原告の誤りを踏襲している部分があることなどから、依拠性が認められました。
ただし、依拠性の有無は個々の事案ごとに慎重に判断される必要があり、単に似ているというだけでは依拠性が認められるわけではありません。
同一性または類似性があること
著作権侵害が成立するためには、侵害が疑われる著作物が既存の著作物と同一であるか、または類似していることが必要です。これを「同一性」または「類似性」と呼びます。
同一性とは、既存の著作物を完全に複製している場合を指します。例えば、他人の文章をそのままコピーしたり、絵画を複製したりする場合が該当します[4]。
一方、類似性は、完全な複製ではないものの、既存の著作物の本質的な特徴を直接感得できる程度に似ている場合を指します。例えば、既存の小説のストーリーを若干変更して小説を書いたり、既存の絵画の構図や色彩を模倣して絵を描いたりする場合が該当します。
類似性の判断基準については、最高裁判所の判決(平成13年6月28日)で示されています。この判決では、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう」とされ、また「著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」とされています。
ただし、アイデアや事実それ自体は著作権法の保護対象ではないため、それらが似ているだけでは著作権侵害にはなりません。保護されるのはあくまで「表現」であり、その表現の本質的な特徴が類似しているかどうかが判断基準となります。
類似性の判断は時に難しく、裁判でも争点となることが多いです。特に、パロディや二次創作の場合など、既存の著作物を参考にしつつも新たな創作性を加えている場合の判断は難しいケースが多くあります。
著作権法で定められた利用行為に該当すること
著作権侵害が成立するためには、著作権法で定められた著作権者の専有する利用行為に該当することが必要です。著作権法は、著作権者に対して様々な権利を付与しており、これらの権利を侵害する行為が著作権侵害となります。
具体的には、以下のような権利が著作権者に認められています:
- 複製権(著作権法21条):著作物を複製する権利
- 上演権、演奏権(同法22条):著作物を公に上演・演奏する権利
- 上映権(同法22条の2):著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権・公衆伝達権(同法23条):著作物を公衆に送信・伝達する権利
- 口述権(同法24条):言語の著作物を公に口述する権利
- 展示権(同法25条):美術の著作物等を公に展示する権利
- 頒布権(同法26条):映画の著作物を頒布する権利
- 譲渡権(同法26条の2):著作物の原作品・複製物を譲渡する権利
- 貸与権(同法26条の3):著作物の複製物を貸与する権利
- 翻訳権、翻案権等(同法27条):著作物を翻訳・翻案等する権利
- 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条):二次的著作物を利用する権利[4]
これらの権利を侵害する行為、例えば著作権者の許諾なく著作物を複製したり、公衆送信したりする行為が著作権侵害となります。
ただし、著作権法には権利制限規定も存在し、一定の条件下では著作権者の許諾なく著作物を利用できる場合があります。例えば、私的使用のための複製(同法30条)、引用(同法32条)、教育目的での利用(同法35条)などが該当します。
また、著作権法には「みなし侵害」の規定もあり、著作権を侵害する行為によって作成された物を、その事実を知りながら頒布したり、頒布目的で所持したりする行為なども著作権侵害とみなされます(同法113条)。
著作権侵害の判断は、これらの権利や制限規定を踏まえて総合的に行われます。そのため、著作物を利用する際は、どの権利に関わる行為なのか、権利制限規定は適用されないのかを慎重に検討する必要があります。
著作権侵害をした場合の罰則について
著作権法では、著作権侵害に対して民事的措置と刑事的措置の両方が定められています。
刑事罰の場合
著作権侵害に対する刑事罰は、侵害の態様によって異なります。
- 著作権、出版権または著作隣接権の侵害(著作権法119条1項)
- 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその併科
- 親告罪
- 著作者人格権または実演家人格権の侵害(著作権法119条2項1号)
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科
- 親告罪
- 技術的保護手段回避装置等の製造等(著作権法120条の2第1号)
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその併科
- 非親告罪
- 違法ダウンロード(著作権法119条3項)
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその併科
- 親告罪
- 著作者名を偽って著作物の複製物を頒布(著作権法121条)
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその併科
- 非親告罪
- 出所明示の義務違反(著作権法122条)
- 50万円以下の罰金
- 非親告罪
「親告罪」とは、著作権者等の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪を指します。一方、「非親告罪」は告訴がなくても公訴を提起できる犯罪です。
また、法人の代表者や法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または個人の業務に関して著作権侵害を行った場合、行為者を罰するほか、その法人または個人に対しても罰金刑が科されます(著作権法124条)。
特に重大な侵害の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科される可能性があります。
民事上の罰則
刑事罰とは別に、著作権者は民事的措置として以下の請求をすることができます。
- 差止請求(著作権法112条)
- 著作権侵害の停止や予防を請求できる
- 損害賠償請求(民法709条)
- 著作権侵害によって生じた損害の賠償を請求できる
- 著作権法114条から114条の5に損害額の推定等の規定がある
- 不当利得返還請求(民法703条、704条)
- 著作権侵害によって得た利益の返還を請求できる
- 名誉回復等の措置の請求(著作権法115条)
- 著作者人格権等を侵害された場合、著作者の名誉回復のための措置を請求できる
これらの民事的措置は、著作権者が自らの権利を守るために行使できる重要な手段です。特に損害賠償請求では、侵害の規模によっては高額な賠償金が命じられる可能性があります。
例えば、2022年に出版大手3社が海賊版サイト「漫画村」の元運営者に対して約19億2960万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。これは、海賊版サイト関連の民事訴訟では過去最大の請求額となりました。
著作権侵害に対する罰則は、著作権者の権利を保護し、創作活動を奨励するために設けられています。しかし、その一方で、これらの罰則が表現の自由や情報の流通を過度に制限しないよう、バランスを取ることも重要です。
そのため、著作権法には「引用」や「私的使用のための複製」など、一定の条件下で著作物を利用できる権利制限規定も設けられています。著作権侵害を避けるためには、他人の著作物を利用する際に常に注意を払い、必要な場合は適切な許諾を得ることが重要です。
また、著作権法の基本的な知識を身につけ、自身の行為が著作権侵害に当たらないかを慎重に判断することが求められます。
著作権侵害とはされない(著作物が自由に使える)場合の事例
著作権が制限される(著作物が自由に使える)場合について、5つの例を挙げ、解説いたします。
私的使用のための複製(著作権法第30条)
私的使用のための複製とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合に、著作物を複製することができるというものです。例えば、自分で楽しむために音楽CDをスマートフォンに取り込んだり、テレビ番組を録画したりすることが該当します。
ただし、この制限にも例外があります。公衆用の自動複製機器を用いる場合や、著作権を侵害する自動公衆送信からの録音・録画、映画館等での録音・録画は認められません。また、違法にアップロードされた音楽や映像を、違法だと知りながらダウンロードすることも禁止されています。
私的使用のための複製は、個人の文化的生活の自由を保障するために認められていますが、著作権者の利益を不当に害することがないよう、その範囲は限定的に解釈されています。
引用(著作権法第32条)
公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であれば、自由に引用することができます。ただし、引用する際には、出所を明示する必要があります。
引用が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります
- 引用する資料等は既に公表されているものであること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う必然性があること
引用は、学術研究や批評活動を促進し、表現の自由を保障するために重要な制度です。ただし、引用の範囲を超えて著作物を利用する場合は、著作権者の許諾が必要となります。
学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
学校その他の教育機関において、授業の過程で使用する場合、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製することができます。また、遠隔授業のために公衆送信することも認められています。
ただし、この制限にも条件があります。
- 1) 営利を目的としない教育機関であること
- 2) 授業を担当する教員やその授業を受ける者が複製すること
- 3) 授業で必要とする限度内であること
- 4) 著作権者の利益を不当に害さないこと
例えば、授業で使用するためにテキストの一部をコピーすることは認められますが、学生全員分のテキストをコピーして配布することは認められません。また、授業で使用した著作物を学内LANに永久保存することも「必要と認められる範囲」を超えるとされています。
図書館等における複製(著作権法第31条)
図書館等では、以下の場合に著作物を複製することができます。
- 1) 利用者の求めに応じ、調査研究のために公表された著作物の一部分を複製する場合
- 2) 図書館資料の保存のために必要がある場合
- 3) 他の図書館等の求めに応じ、絶版等の理由により入手が困難な図書館資料の複製物を提供する場合
ただし、複製できる範囲は著作物の一部分に限られ、定期刊行物に掲載された個々の著作物の場合は全部の複製が可能です。また、デジタル化された著作物の場合、複製物の譲渡は認められません。
この規定は、図書館が果たす公共的な役割と著作権者の利益のバランスを取るために設けられています[1]。
付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2)
写真や動画を撮影する際に、意図せずに背景に著作物が写り込んでしまう場合があります。このような場合、その著作物(付随対象著作物)が写真や動画の主たる対象でなく、かつ著作権者の利益を不当に害しない場合に限り、その利用が認められます。
例えば、街頭インタビューの様子を撮影した際に、背景に看板やポスターが写り込んでしまった場合、それらの著作物の利用は認められます。ただし、意図的にそれらの著作物を撮影の主たる対象とした場合は、この規定の適用外となります。
この規定は、日常的な表現活動の自由を確保するために設けられたものです。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合(例えば、写り込んだ著作物が鑑賞の対象となるほど大きく写っている場合など)は、この規定の適用外となります。
著作権侵害を避けるために行うべき対策方法7つ
著作権侵害を避けるための対策方法を7つ挙げ、それぞれ解説いたします。
著作権に関する正しい知識を身につける
著作権侵害を避けるための最も基本的な対策は、著作権に関する正しい知識を身につけることです。著作権法の基本的な内容、著作物の定義、著作権の保護期間、著作権者の権利などについて理解を深めましょう。
特に重要なのは、著作物の利用に関する規定です。例えば、私的使用のための複製や引用など、一定の条件下で著作権者の許諾なく著作物を利用できる場合があります。これらの例外規定を正しく理解することで、不必要に萎縮することなく、適切に著作物を利用することができます。
また、著作権は国によって異なる部分があるため、国際的な著作権の取り扱いについても基本的な知識を持っておくことが大切です。定期的に著作権に関するセミナーや講習会に参加したり、最新の判例や法改正の情報をチェックしたりすることで、常に最新の知識を維持するよう心がけましょう。
著作権フリーの素材を活用する
著作権フリーの素材を積極的に活用することで、著作権侵害のリスクを大幅に減らすことができます。著作権フリーの素材とは、作者が著作権を放棄したり、一定の条件下で自由に使用を許可したりしている素材のことです。
画像や音楽、イラスト、フォントなど、様々な種類の著作権フリー素材が提供されています。これらを利用する際は、必ず利用規約を確認し、商用利用の可否や、クレジット表記の必要性などの条件を守ることが重要です。
著作権フリー素材を提供するウェブサイトやサービスには、Pixabay、Unsplash、Free Music Archive、Google Fontsなどがあります。これらのサイトでは、高品質な素材を無料で利用できることが多いですが、中には有料のものもあります。予算と必要性に応じて、適切な素材を選択しましょう。
引用ルールを正しく理解し、遵守する
他人の著作物を利用する際、適切な引用は著作権侵害にはなりません。しかし、引用には明確なルールがあり、これを遵守することが重要です。
引用の基本的なルールは以下の通りです。
- 引用の必然性があること
- 引用部分が明確に区別されていること
- 引用部分が従で、自分の著作物が主であること
- 出典を明示すること
引用する際は、原文を一字一句そのまま使用し、改変しないことが原則です。また、引用の量は必要最小限に抑えるべきです。引用部分はかぎ括弧で囲むなどして、自分の文章と明確に区別しましょう。
出典の明示は非常に重要です。書籍の場合は著者名、書籍名、出版社、出版年、該当ページを記載します。ウェブサイトの場合は、サイト名、URL、アクセス日を記載するのが一般的です。
許諾を得る習慣をつける
著作物を利用する際、可能な限り著作権者から許諾を得る習慣をつけることが重要です。特に商用利用の場合は、著作権フリーの素材であっても、念のため許諾を得ることが望ましいでしょう。
許諾を得る際は、以下の点を明確にしておくことが大切です:
- 利用目的
- 利用方法(複製、公衆送信、翻案など)
- 利用期間
- 利用範囲(地域など)
- 対価の有無と金額
許諾を得た際は、書面で記録を残しておくことをおすすめします。メールでのやり取りでも構いませんが、後々のトラブルを避けるため、合意内容を明確に文書化しておくことが重要です。
また、著作権者が不明な場合や連絡が取れない場合に備えて、著作権者不明等の場合の裁定制度についても知っておくと良いでしょう。
著作権管理ツールを活用する
著作権管理ツールを活用することで、自社の著作物の管理や、他者の著作物の適切な利用を効率的に行うことができます。
著作権管理ツールには以下のような機能があります:
- 著作物のデータベース化
- 利用許諾の管理
- 著作権の有効期限の管理
- 著作物の利用状況の追跡
- 著作権侵害の検出
特に大量の著作物を扱う企業や団体にとっては、これらのツールの導入が効果的です。例えば、Adobe Experience Managerなどの大規模なコンテンツ管理システムには、著作権管理機能が含まれていることがあります。
また、インターネット上での著作権侵害を検出するツールもあります。これらのツールを利用することで、自社の著作物が無断で使用されていないかをチェックすることができます。
社内ガイドラインの策定と教育の実施
著作権侵害を組織的に防ぐためには、社内ガイドラインの策定と、従業員への教育が不可欠です。
社内ガイドラインには以下のような内容を含めると良いでしょう:
- 著作権の基本的な説明
- 著作物利用の手順(許諾の取得方法など)
- 引用のルール
- 著作権フリー素材の利用方法
- 著作権侵害が発生した場合の対応手順
ガイドラインを策定したら、定期的に従業員向けの研修を実施し、著作権に関する理解を深めることが重要です。また、著作権法の改正や新しい判例が出た際には、適宜ガイドラインを更新し、従業員に周知することも忘れずに行いましょう。
弁護士など専門家への相談
著作権に関する問題は複雑で、判断が難しいケースも多々あります。そのため、重要な案件や判断に迷う場合は、弁護士や弁理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的リスクの正確な評価
- 適切な対応策の提案
- 最新の法改正や判例の情報提供
- 契約書のチェックや作成支援
また、著作権管理団体(例:JASRAC)に相談することで、特定の分野における著作権の取り扱いについて、詳細な情報を得ることができます。
定期的に専門家とコンサルティング契約を結び、著作権に関する助言を受けることで、より確実に著作権侵害を防ぐことができるでしょう。