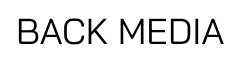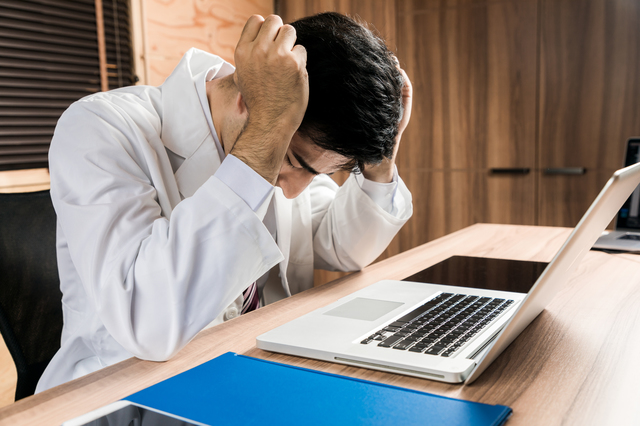業務上横領が発生した場合、被害者である企業が示談で済ませるか、裁判をするかの判断は、様々な要素を総合的に考慮して行う必要があります。企業は、被害額、加害者の態度、証拠の状況、企業イメージ、費用対効果などを慎重に検討し、自社の状況に最も適した解決方法を選択する必要があります。
いずれの選択をするにしても、早期に弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士は、事実関係の調査、証拠収集のサポート 、加害者との交渉 、告訴・告発の手続き 、損害賠償請求訴訟の提起 、再発防止策の策定支援 など、様々な側面から企業をサポートし、最善の解決へと導いてくれます。
本記事では、業務上横領の被害に遭った場合、弁護士に依頼するメリットや選び方、弁護士費用についても詳細に解説します。

業務上横領に強い弁護士の選び方
業務上横領の問題に直面した場合、早期に弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。内部調査の段階から法的アドバイスを受けることで、適切な証拠収集や手続きの進め方について専門的な助言が得られ、後々の紛争リスクを減らすことができます。
どのような弁護士に依頼すべきかですが、本件のような社内不正・刑事事件に関わる問題では以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
大前提|弁護士に共通して重要となる資質
業務上横領事件に限らず、弁護士として共通して求められる重要な資質も、弁護士選びの際に考慮すべき点です。
依頼者とのコミュニケーション能力
弁護士は、法律の専門家として、複雑な法律用語や手続きを依頼者に分かりやすく説明する能力が求められます。依頼者の話を丁寧に聞き、不安や疑問に真摯に答える姿勢も重要です。円滑なコミュニケーションは、依頼者との信頼関係を築き、効果的な弁護活動を行う上で不可欠です。
秘密保持の徹底
弁護士は、依頼者から提供された情報や事件に関する情報を厳格に秘密として保持する義務を負っています。この秘密保持義務は、依頼者が安心して弁護士に相談し、事件の解決を委ねるための基盤となります。
倫理観の高さ
弁護士は、高い倫理観を持ち、公正かつ誠実に職務を遂行することが求められます。依頼者の利益を最優先に考え、不正な手段を用いることなく、法律と正義に基づいて行動することが重要です。
迅速な対応力と可用性
業務上横領事件は、早期の対応が重要となる場合が多いため、弁護士の迅速な対応力は重要な要素です。特に逮捕・勾留されているような緊急性の高い状況においては、すぐに接見に来てくれるなど、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶことが望ましいです。24時間対応可能な弁護士事務所もあります。
信頼関係と相性
弁護士との相性は、事件の解決に向けて二人三脚で取り組む上で非常に重要です。初回相談などを通じて、弁護士の人柄や考え方、コミュニケーションスタイルなどを確認し、信頼できると感じられる弁護士を選ぶことが大切です。
刑法と会社法に精通している
横領問題は、会社内部の法務対応(労務・懲戒・損害賠償)と刑事手続きの双方に関わります。そのため、企業法務全般の知識に加え、刑事事件(特に被害者側の告訴支援や経済犯罪)に強い弁護士が望ましいです。
- 刑法:業務上横領罪(刑法253条)および単純横領罪(刑法252条)の構成要件、法定刑、関連する判例に関する深い理解は不可欠
- 会社法:取締役や監査役などの会社役員の義務や責任、特別背任罪の規定(会社法960条、961条)への理解
「内部不正対応」「コンプライアンス」「ホワイトカラー犯罪」に詳しい法律事務所や、元検察官の経歴を持つ弁護士などが適任と考えられます。実際、業務上横領事件を数多く手掛けている弁護士事務所も存在するため、事前に実績を調べて依頼すると安心です。
会計に関する知識
業務上横領事件の多くは、会社の資金や財産の不正な流用を伴うため、会計の基本的な知識も必要となります。
財務諸表の読み方、帳簿の仕組み、経費精算の流れなどを理解していることで、横領の手口や被害額の特定、証拠の分析がより的確に行えるようになります。
経費の水増し、架空請求、現金の抜き取りなど、典型的な横領の手口を知っていることも重要です。
労務問題にも対応できる
横領事件では懲戒解雇や損害賠償請求といった労務・民事上の対応も必要です。解雇処分に不備があると労働審判等で争われる可能性があるため、労働法にも明るい弁護士だとなお望ましいでしょう。
もっとも、企業法務系の弁護士であれば労務分野も扱うことが多いため、大抵はカバーされると思われます。
豊富な解決実績と経験
業務上横領事件の解決実績が豊富であることは、その弁護士が類似の事件でどのような戦略を取り、どのような結果を出してきたかの指標となります。経験豊富な弁護士は、事件の展開を予測し、適切な対応策を講じることができます。特に、同種事案の示談交渉や裁判での弁護経験は、事件の帰趨を左右する可能性があります。
複雑な事実関係や証拠を分析する高い能力: 業務上横領事件は、多くの場合、複雑な会計処理や資金の流れが絡み合っており、証拠も多岐にわたります。これらの複雑な事実関係や証拠を迅速かつ正確に分析し、事件の全体像を把握する能力に長けています。必要に応じて、フォレンジック調査などの専門家の協力を得ることもあります。
刑事事件に関する深い知識と経験: 横領は刑事事件であるため、刑事事件全般に関する深い知識と経験は不可欠です。逮捕、勾留、起訴といった刑事手続きの流れを熟知していることはもちろん、証拠の収集・分析、捜査機関との交渉、公判での弁護戦略など、刑事弁護に関する専門的な知識とスキルが求められます。
示談交渉力
特に加害者側の弁護においては、被害者である会社との示談交渉が非常に重要になります。被害者の感情や会社の意向を理解し、適切な賠償額や支払い条件などを交渉する能力は、刑事事件化の回避や刑の軽減に大きく影響します。
企業法務に関する知識: 会社が被害者の場合、または加害者が会社の役員や従業員である場合、企業法務に関する知識も重要となります。会社の組織構造、内部統制、会計処理などに関する理解は、事件の背景を把握し、適切な法的アドバイスを行う上で役立ちます。
業務上横領に強い弁護士を探せるおすすめのサービス5選比較
業務上横領に強い弁護士を探すために役立つ5つのサービスの特徴と活用方法について詳しく解説します。
弁護士選びの際は、業務上横領の実績や企業法務の経験、費用体系を確認することが重要です。また、初期相談を通じて相性や信頼関係を確かめた上で依頼することをお勧めします。
企業法務弁護士ナビ

企業法務弁護士ナビは、企業法務に特化した弁護士を探せる専門性の高いサービスです。業務上横領事案は企業内で発生することが多く、企業法務の一部として扱われるため、このサービスは横領問題の解決に適した弁護士を見つける上で大変有用です。
公式サイト:https://houmu-pro.com/
サービスの特徴は、企業法務の専門性を持つ弁護士に特化している点にあります。検索結果からは、取引契約や企業間紛争の解決などに実績のある弁護士を見つけられることがわかります。業務上横領事案では、証拠収集から従業員への法的対応、損害回収まで幅広い法的サポートが必要ですが、企業法務の経験豊富な弁護士はこれらの対応に長けています。
横領事案の場合、内部調査から始まり、従業員への懲戒処分、損害賠償請求、さらには刑事告訴まで検討する必要があり、企業法務の専門知識が重要です。企業法務弁護士ナビでは、事例や専門分野から弁護士を絞り込むことができるため、過去に業務上横領の処理経験がある弁護士を効率的に見つけることが可能です。
また、業務上横領は企業のガバナンスや内部統制と密接に関係しているため、単に事後対応だけでなく、再発防止策の構築においても企業法務に詳しい弁護士のアドバイスが有用です。
このサービスを利用する際には、業務上横領の取扱実績や企業の内部不正対応の経験について具体的に確認するとよいでしょう。企業法務弁護士ナビは、横領問題に関して総合的なリーガルサポートを提供できる弁護士を見つける上で、効果的なプラットフォームといえます。
公式サイト:https://houmu-pro.com/
弁護士会
弁護士会は各地域の弁護士が所属する自治組織であり、業務上横領に強い弁護士を探す際の信頼できる窓口となります。弁護士会では、法律相談センターや弁護士紹介制度を通じて、専門性に応じた弁護士の紹介を行っています。
弁護士会の最大の強みは、公的性格を持つ組織であるため、中立的な立場からの弁護士紹介が受けられる点です。業務上横領のような専門性の高い案件では、多くの弁護士会が「専門分野別名簿」を作成しており、企業法務や刑事事件に精通した弁護士を紹介してくれます。
業務上横領事件では、証拠の収集・保全から始まり、従業員への対応、損害賠償請求、刑事告訴など多岐にわたる法的手続きが必要となりますが、弁護士会ではこれらの手続きに精通した弁護士を探すことができます。特に刑事告訴の経験が豊富な弁護士や、企業内不正に詳しい弁護士を紹介してもらえる可能性が高いです。
また、弁護士会では無料や低額で初回相談を受けられる法律相談センターを運営していることも多く、業務上横領が疑われる段階での相談にも適しています。さらに、弁護士会を通じた紹介は、弁護士の専門性や経験が一定水準以上であることがある程度担保されているため、安心して相談できる点もメリットです。
弁護士会を利用する際は、まず地域の弁護士会に連絡し、業務上横領や企業法務に詳しい弁護士の紹介を依頼するとよいでしょう。事案の概要を説明することで、より適切な弁護士の紹介を受けられる可能性が高まります。
弁護士ドットコム

弁護士ドットコムは国内最大級の法律相談ポータルサイトであり、業務上横領に強い弁護士を探す上で非常に便利なプラットフォームです。このサービスは、「弁護士検索」機能により、地域や専門分野から弁護士を探すことができ、国内の弁護士の半数以上が登録しているという規模の大きさが強みです。
業務上横領事案に取り組む際には、弁護士の専門性や過去の実績が重要なポイントになりますが、弁護士ドットコムでは各弁護士の詳細なプロフィールを確認できます。個々の弁護士の注力分野、解決事例、さらには料金表まで閲覧可能であり、業務上横領の解決実績がある弁護士を効率的に見つけることができます。
特に有用な機能が「みんなの法律相談」です。業務上横領について疑問や初期段階での相談を無料で行うことができ、専門の弁護士から回答を得られます。これにより、本格的な相談の前に、自社の状況がどのような法的問題を含んでいるのか、どういったアプローチが考えられるのかを事前に把握できます。
また、実際に利用した方の感謝の声や評価も確認できるため、弁護士選びの参考になります。業務上横領のような繊細な案件では、弁護士との相性や信頼関係も重要なファクターですが、過去のクライアントの声はそうした情報を得る上で貴重な手がかりとなります。
さらに、弁護士費用の一括見積り機能もあり、複数の弁護士に同時に見積りを依頼できるため、費用面での比較検討も容易です。業務上横領事案では、調査費用や交渉着手金など様々な費用が発生しますが、この機能を利用することで適切な予算計画を立てることができます。
ココナラ法律相談

ココナラ法律相談は、会員数400万人以上を誇るココナラが運営する弁護士検索ポータルサイトであり、業務上横領に強い弁護士を探す際に独自の強みを持つサービスです。詳細な地域設定や細かく紐付けされた分野での検索が可能であるため、業務上横領という特定の専門分野に強い弁護士を効率的に見つけることができます。
このサービスの最大の特徴は「おしえて!法律Q&A」機能の使いやすさです。業務上横領が疑われる段階で、匿名・公開・無料で相談を投稿でき、弁護士からのアドバイスを得ることができます。また、他のユーザーによる同様の相談内容や弁護士からの回答も閲覧できるため、業務上横領の初期対応や法的リスクについての理解を深めることができます。
ココナラ法律相談では、投稿にハッシュタグが付けられているため、「業務上横領」「企業不正」などのキーワードで関連相談を簡単に検索できる点も便利です。これにより、似たような事例における弁護士のアドバイスや対応策を参照することができ、自社の状況に適用できる知見を得ることができます。
また、「弁護士検索から依頼までの流れ」が詳しく解説されているため、初めて業務上横領の法律相談をする企業担当者でも安心してサービスを利用できます。業務上横領事案では、証拠の確保から始まり、調査、損害賠償請求、刑事告訴など多岐にわたるプロセスが必要となりますが、そうした一連の流れを理解した上で適切な弁護士を選ぶことができます。
ココナラ法律相談を活用する際は、業務上横領に関する過去の相談内容を確認した上で、自社の状況に最も近い問題に対応した経験を持つ弁護士を見つけることが効果的です。また、質問投稿を通じて複数の弁護士から回答を得ることで、それぞれのアプローチや専門性を比較検討することもできます。
ベンナビ刑事事件

ベンナビ刑事事件は、株式会社アシロが運営する弁護士検索サイト「ベンナビ」の専門特化型サービスの一つで、刑事事件に特化しており、業務上横領事案に対応できる弁護士を見つける上で非常に効果的なプラットフォームです。このサービスは「横領事件を得意とする弁護士も多数掲載」していることが大きな強みです。
ベンナビの特徴は、テーマに応じた専門的な検索サイトを用意していることで、刑事事件に特化したベンナビ刑事事件では、業務上横領という特定の犯罪類型に精通した弁護士を効率的に見つけることができます。業務上横領は刑法第253条で規定される犯罪であり、最大10年以下の懲役という重い刑罰が科される可能性があるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士のサポートが重要です。
公式サイト:https://keiji-pro.com/
ベンナビ刑事事件では、「初回相談料が無料の事務所もあります」と記載されており、費用面での不安を抱えずに相談できる点も魅力です。業務上横領事案では、調査費用や交渉着手金など様々な費用が発生しますが、まずは無料で状況を相談できることは大きなメリットといえます。
また、「法律相談Q&A」機能では、業務上横領に関する疑問や悩みを投稿し、弁護士から回答を得ることができます。これまで15,000件以上の相談が掲載されているため、自社の状況に似た事例を参照することも可能です。
業務上横領事案では、証拠の保全から始まり、損害賠償請求、刑事告訴など複雑な法的手続きが必要となりますが、ベンナビ刑事事件では、こうした一連のプロセスに精通した弁護士を見つけることができます。特に刑事告訴を検討している場合や、すでに捜査が始まっている場合など、刑事手続きの側面が強い事案において、このサービスは大いに役立ちます。
公式サイト:https://keiji-pro.com/
業務上横領について弁護士に依頼した際のメリット
業務上横領は企業に深刻な被害をもたらす可能性がある問題です。発生時には証拠収集から始まる適切な対応手順を踏むことが重要であり、予防策としては内部統制システムの強化やコンプライアンス研修の徹底などが効果的です。
また、弁護士に依頼することで証拠収集のサポートから法的手続きの代行まで、専門的な支援を受けられるメリットがあります。以下にその詳細を解説します。
証拠収集のサポート
業務上横領事件において、証拠収集は最も重要なステップですが、証拠となる物やその収集方法がわからないケースも多いです。弁護士に依頼すれば、どのような証拠が必要か、どう収集すべきかについて専門的なサポートを受けられます。
証拠収集は弁護士の主戦場ともいうべき分野であり、効果的な証拠を適切に収集することで、その後の対応がスムーズになります。また、弁護士は証拠の証明力や有効性についても専門的な知識を持っているため、法的手続きで有効な証拠を確保できます。
とるべき法的手段の明確化
横領をした加害者の責任を追及する手段として、民事上の請求、刑事告訴、社内での懲戒処分などがありますが、どの手段が最適かの判断は容易ではありません。弁護士に相談することで、事案の内容や状況に応じた最適な対応策を提示してもらえます。
特に刑事事件に強い弁護士であれば、刑事告訴を行うことで加害者にプレッシャーをかけ、返金される可能性を高めることもできます。弁護士は刑事・民事両面からの対応が可能なため、総合的な解決策を提案してもらえます。
法的手続きや交渉の代行
弁護士に依頼することで、法的手続きや加害者との交渉を一任できるため、大幅に負担を軽減できます。企業の担当者が直接交渉するよりも、弁護士が間に入ることで冷静かつ客観的な交渉が可能となり、早期解決につながります。
特に示談交渉の場合、弁護士が行うと成立する可能性が高まります。弁護士は同種の示談経験を多く持っているため、会社の中の誰を相手に話を進めるべきか、会社の対処方針を確認しながら慎重に交渉を進めることができます。
横領被害の回収可能性の向上
弁護士を通じて示談交渉を行うことで、横領された金銭の回収可能性が高まります。弁護士が介入することで、加害者は法的リスクを認識し、被害弁償に応じる可能性が高くなります。
また、加害者の支払能力が不足している場合でも、弁護士は給与との相殺や退職金の不支給など、様々な回収方法を提案できます。さらに、法的手続きを通じた強制執行なども視野に入れた対応が可能となります。
損害賠償請求
弁護士は、業務上横領によって会社が被った損害の回復を目指し、加害者に対して損害賠償を請求する活動を行います. まずは、加害者との間で示談交渉を行い、被害金額の返還や慰謝料などの支払いを求めます。
弁護士は、会社の損害額を正確に算定し、法的な根拠に基づいて交渉を進めます. 示談交渉が不調に終わった場合には、民事訴訟を提起し、裁判所を通じて損害賠償を請求することになります。
訴訟においては、証拠に基づいて会社の損害を立証する必要があり、弁護士は訴状の作成、証拠の提出、法廷での主張など、訴訟手続き全般をサポートします。 損害賠償請求を通じて、会社は経済的な損失を回復し、加害者に対して法的な責任を追及することができます。
適切な対応による二次被害の防止
業務上横領への対応を誤ると、不当解雇として訴えられるなどの二次的なリスクが生じる可能性があります。弁護士に依頼することで、適切な手続きを踏んだ対応ができ、こうしたリスクを回避できます。
また、証拠が不十分な状態で解雇や訴訟を行った場合、解雇の無効を主張される可能性や、訴訟でも請求が認められない可能性があります。弁護士のサポートにより、十分な証拠に基づいた適切な対応が可能となります。
従業員の解雇手続き
弁護士は、業務上横領を行った従業員に対する懲戒解雇などの解雇手続きについて、法的なアドバイスを提供します。従業員の不正行為を理由に解雇する場合、労働契約法や就業規則に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。
不適切な手続きで解雇した場合、従業員から不当解雇として訴訟を起こされるリスクがあります。弁護士は、解雇理由の正当性、解雇手続きの適法性などを確認し、会社が法的なリスクを負うことなく解雇手続きを進められるようにサポートします。
具体的には、就業規則の確認、解雇理由書の作成、従業員との面談への同席などを行います。適切な解雇手続きを行うことは、会社を守る上で非常に重要です
再発防止策の策定支援
弁護士は多くの横領事件を取り扱っているため、効果的な再発防止策についても専門的なアドバイスが可能です。
今回の事件の原因や背景を分析し、内部統制の改善すべき点を洗い出します。その上で、具体的な再発防止策を提案します。例えば、会計処理の厳格化、複数担当者によるチェック体制の導入、内部監査の実施、従業員に対するコンプライアンス教育の実施などが考えられます。
弁護士は、これらの対策が法令や会社の状況に適合しているかを確認し、実効性のある再発防止体制の構築をサポートします。再発防止策を講じることは、会社の信頼性を高め、将来的な損失を防ぐために不可欠です。
業務上横領の被害で弁護士に依頼する際の費用
相談料の相場
例えば咲くやこの花法律事務所では、初回相談料を30分5,000円(税抜)に設定し、顧問契約を締結した場合は相談料が無料になるサービスを提供しています。
- ※相談料はその場で支払うケースが多く、相談だけで正式依頼に進まなくても問題ありません。
- 初回無料相談を上手に活用し、複数の弁護士から見積もりや方針を聞いて比較検討すると良いでしょう。
被害届・告訴状の作成および代理提出の費用
横領被害について被害届や告訴状の作成を弁護士に依頼する場合、費用は案件の難易度や証拠の整理量によって幅がありますが、おおよそ20万~80万円程度が相場とされています。行政書士に書面作成のみ依頼する方法もありますが、弁護士と違い代理提出や警察対応はできないため、被害申告を確実に受理してもらうには弁護士への依頼が望ましいでしょう。
実際の費用は事案の複雑さによりますが、数十万円規模の予算を見込んでおく必要があります。
- ※被害届・告訴状作成の費用は依頼時に着手金として前払いするのが一般的で成功報酬は設定されないか、受理・起訴など結果に応じ別途報酬金を請求されるケースもあります。
- 依頼前に費用の内訳(書面作成のみか、警察対応含むか)を明確に確認しましょう。
示談交渉の代理費用(成功報酬や時間制など)
加害者との示談交渉を弁護士に代理依頼する場合、弁護士費用の計算方法としては大きく分けて「成功報酬制(成果ベース)」「時間制(タイムチャージ)」「定額制」のいずれか、または組み合わせで設定されます。
横領被害の示談交渉では、被害額の返還や慰謝料の取得といった経済的利益に対する成功報酬が用いられることが多く、得られた示談金の約10~20%を報酬金とする事務所が一般的です。
一方、時間制料金で対応する弁護士もおり、その際の時間単価は事務所や弁護士の経験によりますが、1時間あたり数万円程度(目安:2~5万円)の設定が多いようです(この場合、交渉に要した時間分の費用を支払います)。
- ※示談交渉の費用支払いは、成功報酬制であれば示談成立後に報酬金を支払います
- 時間制の場合は月末締めなどで実働時間分を精算する形が一般的です。依頼時に成功報酬割合や時間単価、示談不成立時の費用有無を必ず確認しておきましょう。
損害賠償請求(民事訴訟)の着手金・報酬金
横領による損害返還や賠償金を民事訴訟で請求する場合、弁護士費用は他の金銭請求事件と同様に着手金+報酬金で設定されるのが一般的です。着手金とは事件を依頼する際に支払う初期費用で、請求額(経済的利益)の5~8%程度が目安となることが多いです(※法定の定めはなく事務所ごとに異なります)。
実務的には、請求額が大きいほど割合は低めに抑えられる傾向があります。
(例:1,000万円の請求なら着手金約5%≒50万円、報酬金約10%≒100万円が目安)
なお近年は報酬基準が自由化されたため、着手金0円(成功報酬のみ)や低額の着手金+高めの成功報酬など柔軟な料金設定をする法律事務所もあります。依頼前に必ず見積もりを取り、着手金・報酬金の金額やパーセンテージを確認しましょう。
- ※民事訴訟における着手金は訴訟提起時までに前払いし、報酬金は判決確定や和解成立後に支払います
- 訴訟費用にはこのほか実費(印紙代や郵送代等)も発生しますが、勝訴すれば一部を相手方に請求可能です。
顧問契約時の月額料金相場と含まれる業務範囲
継続的に弁護士のサポートを受ける場合は顧問契約を結ぶ選択肢もあります。顧問契約の月額料金は事務所規模や業務範囲により様々ですが、中小企業向けでは月額3~5万円程度が一般的な相場と言われています。日弁連のアンケート(2009年)でも「月3時間程度の相談を含む顧問料」のボリュームゾーンは月額5万円で、次いで3万円との回答が多く、顧問料は「数万円台」が中心です。
業務範囲は契約内容によって異なりますが、月数時間分の法律相談や簡易な文書チェックなどは顧問料内で追加費用なく対応する事務所が過半数を占めます。
月額顧問料自体は契約期間にわたり毎月定額を支払います(支払い方法は月末締翌月払いなど様々)。企業規模によっては月額10万円以上のプランや、逆に個人事業主向け1~2万円程度のライトプランを用意している事務所もあります。自社の法務ニーズに応じて適切なプランを選ぶことが重要です。
- 顧問契約を結ぶことで日常的な法律相談がしやすくなり、問題の早期発見・予防につながるメリットがあります。
- 費用面でも都度依頼よりトータルコストが下がるケースが多いですが、月額料金に見合う利用頻度があるか検討しましょう。
業務上横領発生時の企業の判断基準:示談と裁判の選択
業務上横領が発生した場合、被害者である企業は「示談で解決するか」「刑事告訴や民事裁判に進むか」という重要な判断を迫られます。この判断は企業の将来に大きな影響を与えるため、様々な要素を考慮した慎重な検討が必要です。
企業が示談と裁判のどちらを選択すべきかを判断するためのフレームワークを以下に示します。
- 被害状況の精査
- 横領額の確定: 正確な被害金額を把握する
- 横領の手口と期間: 単発か継続的か、手口の巧妙さ
- 関与者の特定: 単独犯か複数関与か
- 内部統制の問題点: 横領を許した組織的要因の分析
- 加害者の状況評価
- 反省の度合い: 真摯に反省しているか
- 弁済能力: 一括返済が可能か、分割なら何年で完済できるか
- 社内での立場: 役職や勤続年数、信頼関係
- 再犯リスク: 過去の不正行為の有無、性格特性
- 企業への影響分析
- 金銭的影響: 横領額が企業経営に与える影響の大きさ
- レピュテーションリスク: 事件公表による社会的信用への影響
- 社内モラルへの影響: 他の従業員の士気や倫理観への影響
- ステークホルダーの反応: 株主、取引先、顧客の予想される反応
- 法的・実務的検討
- 証拠の十分性: 刑事告訴や民事訴訟に耐える証拠があるか
- 時効の問題: 刑事訴訟(7年)や民事訴訟の時効が迫っているか
- 費用対効果: 裁判に要するコストと回収可能額の比較
- 社内リソース: 裁判対応に割けるリソースの有無
企業が示談と裁判のどちらを選択すべきかの判断基準について詳細に解説します。
示談を選択する場合
示談は裁判所の手続きによらずに、当事者間で話し合いを行い、合意によって紛争を解決する方法です。業務上横領事件における示談は、一般的に、加害者が被害者である企業に対して被害額の弁償や慰謝料を支払い、企業が加害者の刑事告訴を取り下げたり、民事訴訟を提起しないことを約束したりする内容となります。
迅速な解決・早期の決着を望むか
裁判に比べて、示談は一般的に短期間で解決することが可能です。裁判は何ヶ月、あるいは何年にも及ぶ可能性がありますが、示談であれば、当事者間の合意が成立すれば比較的早期に紛争を終結させることができます。早期解決は、企業が本業に集中し、事業活動を円滑に進める上で重要です。
被害金額の回収可能性
企業が示談を選択する最も重要な理由の一つは、横領された金銭の早期回収です。刑事告訴や民事裁判では、判決を得るまでに時間がかかり、さらに判決後も加害者に資力がなければ強制執行をしても回収できない可能性があります。
一方、示談では以下のメリットがあります。
- 被害金額の全額または一部を早期に回収できる可能性がある
- 分割払いなど柔軟な返済計画を交渉できる
- 示談書という法的拘束力のある文書で返済を約束させられる
特に、横領した従業員が返済能力を持っている場合や、親族などからの援助が期待できる場合には、示談による解決が金銭回収の観点から有利となります。
社会的評価・レピュテーションの保護
業務上横領事件を刑事告訴した場合、公開の法廷で審理されるため、企業の内部問題が公になります。これにより以下のリスクが生じます。
- 業務上横領を許した内部管理体制の不備が明らかになる
- 会社の社会的信用が害される
- 投資判断に悪影響を及ぼす可能性がある
特に上場企業や社会的信用が重要な業種(金融機関、教育機関など)では、事件の公表によるレピュテーションリスクを避けるため、示談による内部解決を選択するケースが多いです。
時間的・人的コストの費用対効果
裁判には、弁護士費用、訴訟費用、時間的コストなど、多大な費用がかかります。一方、示談であれば、これらの費用を大幅に削減できる可能性があります。特に、被害額が比較的少額な場合や、早期に解決したい場合には、示談の方が費用対効果が高いと言えます。
刑事告訴や民事裁判を行う場合、企業側には以下の負担が生じます。
- 捜査協力のための資料提供や事情聴取への対応
- 裁判に関わる証拠収集や証言準備
- 社内調査や法的手続きに関わる人的リソースの割当て
これらの時間的・人的コストは、企業の本来の事業活動を阻害する要因となります。示談であれば、こうした負担を最小限に抑えながら問題解決を図ることができます。
加害者の反省度と再発防止効果
加害者が以下の条件を満たす場合、示談による解決が適切な選択となる可能性があります。
- 横領行為を認め、真摯に反省している
- 被害弁償の意思が明確である
- 初犯であり、横領額が比較的少額である
このような場合、刑事罰を科さなくても、示談による解決が十分な再発防止効果をもたらす可能性があります。また、社内の他の従業員に対しても、「横領は許さないが、反省と弁償があれば厳罰に処さない」という企業姿勢を示すことができます。
示談のデメリットは?
- 全額回収の保証がない:示談交渉が必ずしも企業の望む条件で成立するとは限りません。加害者の資力によっては、被害額全額の弁済を受けることが難しい場合もあります。また、慰謝料の支払いを拒否される可能性もあります。
- 加害者の反省が不十分な場合:加害者が表面的には謝罪や弁償の意思を示していても、内面的には反省していない場合や、再犯の可能性が否定できない場合があります。このような場合、示談で済ませることは、企業にとって将来的なリスクとなる可能性があります。
- 社会的な制裁が不十分:業務上横領は犯罪行為であり、社会的な非難を受けるべき行為です。示談で解決した場合、加害者は刑事罰を受けることなく社会生活を送ることができるため、企業や社会にとって十分な制裁とならない可能性があります。
- 他の従業員への影響:業務上横領を安易に示談で済ませてしまうと、他の従業員に対して「不正をしても大した処分にならない」という誤ったメッセージを送ってしまう可能性があります。これは、企業全体の倫理観の低下につながる恐れがあります。
裁判(刑事告訴・民事訴訟)を選択する場合の判断基準
裁判による解決には、刑事告訴による刑事裁判と、損害賠償請求訴訟による民事裁判の2種類があります。
刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。業務上横領罪は刑法に定められた犯罪であり、告訴を受理した捜査機関は捜査を行い、証拠が揃えば加害者を起訴し、刑事裁判が行われます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 加害者への制裁: 刑事裁判で有罪判決が確定すれば、加害者は懲役刑などの刑事罰を受けることになります。これは、企業にとって不正行為に対する抑止力となり、社会正義の実現にもつながります。 企業イメージの回復: 刑事告訴を通じて、企業が不正行為に対して毅然とした態度を示していることを社会に示すことができます。これは、企業の信用回復につながる可能性があります。 被害回復の可能性: 刑事裁判の結果、加害者に罰金刑が科された場合、その一部が被害者である企業に還付されることがあります。ただし、被害額全額が回復するとは限りません。 再発防止への意識向上: 刑事事件として扱われることで、加害者だけでなく、他の従業員に対しても不正行為に対する意識を高める効果が期待できます | 時間と労力:刑事裁判は、捜査から判決まで長期間を要する場合があります。企業は、捜査への協力や証人としての出廷など、多くの時間と労力を費やす必要があります。 費用:刑事告訴の手続き自体には費用はかかりませんが、弁護士に告訴状の作成や捜査機関との連携を依頼する場合には、弁護士費用が発生します。 立証の困難性:刑事裁判では、検察官が加害者の犯罪事実を厳格に立証する必要があります。証拠が不十分な場合や、加害者が否認を続けた場合などには、有罪判決を得られない可能性もあります。 企業イメージへの影響:刑事事件として報道されることで、企業のイメージが損なわれる可能性があります。特に、上場企業や社会的な注目度の高い企業の場合には、その影響は大きいと言えます。 |
横領額の規模と悪質性
以下のような場合、刑事告訴を含む法的手続きが適切な選択となります。
- 横領額が高額(数千万円以上)である
- 長期間にわたって計画的に行われた
- 複数の従業員が関与している組織的な不正である
特に被害額が大きく、加害者の資力では全額弁済が見込めない場合、刑事告訴によって法的制裁を求めることが適切です。
示談交渉の難航・不成立
加害者が以下のような態度を示す場合、示談による解決は困難であり、法的手続きを検討すべきです。
- 横領の事実を否認している
- 弁済の意思がない、または能力がない
- 不誠実な態度や言い逃れを続けている
示談交渉が難航し、合意に至る見込みがない場合は、刑事告訴や民事訴訟による解決を検討する必要があります。
企業のコンプライアンス姿勢の明示
企業が社内外に対して「不正行為には厳正に対処する」というコンプライアンス姿勢を示す必要がある場合、刑事告訴は有効な選択肢となります。特に以下のような状況では、毅然とした対応が求められます。
- 過去に類似の不正行為が発生している
- 企業の信頼回復が必要な状況にある
- 同業他社で不正が多発しており、牽制効果が必要
刑事告訴をすることで、企業が犯罪に対して毅然とした態度を示し、危機管理意識やコンプライアンス意識の高さをアピールすることができます。
再発防止と抑止効果
横領事件の再発を防止するためには、厳格な対応が必要な場合があります。特に以下のような状況では、刑事告訴による厳正な対処が有効です。
- 社内に横領を軽視する風潮がある
- 過去の内部処理では効果がなかった
- 他の従業員への抑止効果が必要
刑事告訴により、「業務上横領は犯罪であり、厳しい処罰を受ける」という認識を社内に浸透させることができます。
示談と裁判の併用アプローチ
実務上は、示談と裁判を完全に二者択一で考えるのではなく、両者を組み合わせた対応も効果的です。
条件付き示談アプローチ
- まず示談交渉を開始し、期限を設定する
- 期限内に合意に至らない場合は刑事告訴する方針を伝える
- 示談条件として「全額弁済」だけでなく「再発防止への協力」も含める
このアプローチにより、加害者に真摯な対応を促しつつ、企業としても複数の選択肢を確保できます。
段階的対応アプローチ
- 初期段階では社内処分と示談交渉を並行して進める
- 示談が成立しない場合や悪質性が高い場合は民事訴訟へ移行
- 特に悪質な場合や社会的影響が大きい場合は刑事告訴も検討
状況の変化に応じて対応を段階的に強化することで、柔軟かつ効果的な問題解決が可能になります。
実例に基づく判断基準の適用
新潟の法律事務所の解決事例では、10年以上にわたり総額1000万円以上の横領を行った従業員のケースがありました。この事例では、弁護士を通じた示談交渉により、被害弁償金を支払う代わりに刑事上の責任を追及しない内容の示談が成立しています。
この事例から、以下の判断基準が重要であることがわかります。
- 迅速な対応: 早期に示談交渉を開始することで解決の可能性が高まる
- 専門家の関与: 弁護士を介することで効果的な交渉が可能になる
- 実質的な被害回復: 金銭的な弁償が示談成立の鍵となる
結論:企業の最適な判断のために
業務上横領が発生した場合、企業は以下のステップで対応を検討すべきです:
- 事実関係の徹底調査: 横領の規模、手口、関与者を正確に把握する
- 専門家への相談: 早期に弁護士などの専門家に相談し、選択肢を整理する
- 総合的な判断: 金銭回収、社会的影響、再発防止などの観点から最適な対応を選択する
- 一貫した対応: 一度方針を決めたら、ブレずに対応を進める
示談と裁判のどちらが適切かは、個々の事案によって異なります。横領額が比較的少額で加害者に弁済能力と反省の態度がある場合は示談が有利であり、横領額が高額で悪質性が高い場合や再発防止の観点から厳正な対処が必要な場合は裁判が適切です。
表1:示談と裁判の比較
| 項目 | 示談 | 裁判(刑事・民事) |
|---|---|---|
| 目的 | 早期解決、費用削減、柔軟な解決内容、秘密保持、刑事告訴の見送り | 加害者への制裁(刑事)、被害回復(民事)、社会的責任の遂行 |
| 手続き | 当事者間の話し合いによる合意 | 捜査機関による捜査、検察官による起訴、裁判所による審理・判決(刑事)、原告による訴訟提起、裁判所による審理・判決(民事) |
| 期間 | 短期間で解決可能 | 長期間を要する可能性あり |
| 費用 | 比較的低額 | 高額になる可能性あり |
| 結果 | 当事者間の合意内容による | 有罪・無罪判決、刑罰(刑事)、勝訴・敗訴判決、損害賠償命令(民事) |
| 公開性 | 非公開 | 原則公開 |
| 被害回復 | 交渉次第で可能だが、全額回収の保証はない | 刑事裁判では不確実、民事裁判では可能だが、加害者の資力による |
| 加害者への制裁 | 限定的 | 刑事罰による制裁が可能 |
| 企業イメージ | 比較的影響が少ない | 報道などにより悪化する可能性あり |
| 弁護士の関与 | 必要に応じて | 強く推奨される |
いずれの選択においても、「被害の回復」「再発防止」「企業価値の保全」という三つの目標をバランスよく達成することが重要です。そのためには、初動対応から解決までの各段階で、法的・経営的・人的側面を総合的に考慮した判断が求められます。
業務上横領は企業にとって深刻な問題ですが、適切な対応によって被害を最小限に抑え、むしろ内部統制を強化する契機とすることも可能です。状況を冷静に分析し、企業の将来を見据えた判断を行うことが、経営者に求められる責任といえるでしょう。