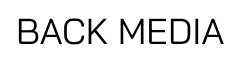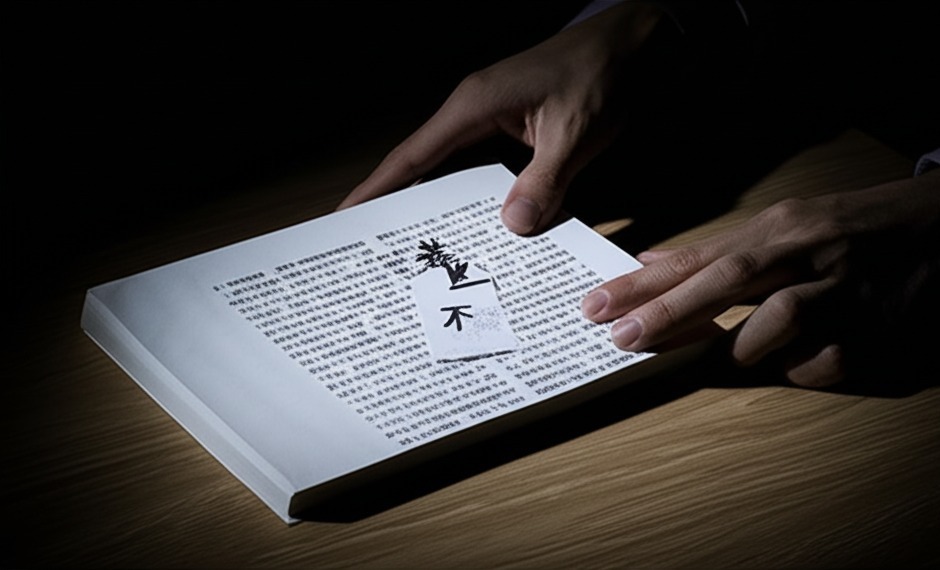業務上横領とは、刑法第253条で定義される犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領する」ことをいい「10年以下の懲役」に課せられます。罰金刑の選択肢はなく、起訴され有罪となれば基本的に懲役刑が科される重い罪です。
わかりやすく言うと、仕事上預かって管理している他人の財産を自分のものにしてしまう行為で、企業経営に深刻な損害をもたらす重大な経済犯罪です。
(業務上横領)
引用元:刑法
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
近年では、経理担当者や役員による巨額横領事件が相次ぎ報道され、企業の内部統制の脆弱性や再発防止策への注目が高まっています。
本記事では、業務上横領の法的定義・構成要件から、実際の刑罰・判例、近年の事件事例、企業が講じるべき対応策、さらには弁護士への相談方法や費用感まで、実務に直結する観点で網羅的に解説します。
信頼を損なわない組織づくりの一助として、ぜひご活用ください。

業務上横領に問われた主要なニュース
業務上横領罪に関する重要判例としては、前述した「業務」の解釈を示した最高裁判例(昭和23年6月5日)があります。この判例により「社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務」が業務と定義され 、会社員に限らず継続的な事務処理を行う立場であれば業務上横領罪の主体(業務上横領をし得る立場)になりうることが確認されました。
元弁護士による業務上横領:被害総額約9200万円
B型肝炎訴訟の弁護団口座から巨額の資金が消えていた事件で、当時弁護団長を務めていた元弁護士、内川寛(うちかわ ひろし:63歳)が業務上横領の疑いで逮捕されました。
容疑者は2021年から2023年にかけて弁護団の預り金約5,000万円を着服し、自身の住宅ローン返済や事務所経費に流用していたとされています。この男性は以前にも同様の着服を繰り返しており、累計被害額は約9,200万円に上る見込みです。信託すべき立場の弁護士による犯行という点で社会的衝撃を与えました。
参考:「弁護団長」を横領容疑で3回目の逮捕 被害総額約9200万円か
82回にわたるインターネットバンキングで2億1000万円を横領した疑い
神戸市のある自動車販売会社で経理を一人で任されていた男性社員(発覚時には退職済、47歳)が、在職中の1年間に計82回もの不正振込を行い、総額約2億1,000万円を横領していた事件が明らかになりました。
男性は社用口座から自身の口座へオンライン振込を繰り返し、その金を「海外FXで儲けようと思った」と供述。会社が異常に気付き内部調査後に警察へ被害を申告し、男性は逮捕・起訴されました。被害額が2億円を超える極めて悪質な内部不正事件として注目されています。
参考:「海外FXで儲けたかった」勤務先から横領疑いで逮捕の男 県警が約2億1000万円の被害裏付け
兵庫県造園建設業協会の元事務員が9797万円の着服
兵庫県造園建設業協会の元事務員の女性(43歳)が、協会の預金口座から約9,797万円もの資金を私的に引き出し、自身のクレジットカード支払い等に充てていた事件で、神戸地方裁判所はこの女性に対し懲役4年(実刑)の判決を言い渡しました。
犯行は15年にわたり常習的に行われており、女性は公判で起訴内容を認めています。裁判所は「長期間にわたり一人で預金口座管理を担う立場を悪用した巧妙悪質な犯行」であること、「横領により協会が経営破綻の危機に陥り被害が甚大」であることを指摘し、実刑4年の量刑を科しました。この判決は、長期に及ぶ巨額横領に対する厳しい姿勢を示すものとして報じられました。
以上のように、近年でも企業や団体における横領事件は後を絶ちません。被害額は数十万円程度の比較的小規模なものから、億単位に及ぶ極めて悪質なものまで様々であり、職種も民間企業の従業員から弁護士、教職員、公務員まで幅広く発生しています。
いずれの場合も、内部統制の不備や一人に権限が集中していたことが犯行を許した一因と指摘されており、各組織での再発防止策の徹底が課題となっています。
参考:兵庫県造園建設業協会 約1億円着服 元事務員の女に懲役4年判決
業務上横領罪と背任罪の区別に関しても数多くの裁判例で議論されていますが、占有する他人財産の有無や本人に経済的損害を与える意図の有無などを基準に区別する考え方が示されています。企業の不祥事では横領と背任が併せて問題になることもありますので、ケースによって適用罪名が分かれる点には注意が必要です。
業務上横領の罰則と定義・構成要件とは
下記の要件を満たすと業務上横領罪が成立します。たとえば「会社から経理担当として預けられている現金をこっそり抜き取って使う」行為は、この定義にそのまま当てはまります。
刑罰
業務上横領罪の法定刑(法律上定められた罰則)は「10年以下の懲役」です。罰金刑の選択肢はなく、起訴され有罪となれば基本的に懲役刑が科される重い罪です。
これは、業務と無関係の単純な横領(刑法252条:5年以下の懲役)に比べて加重された刑です。つまり、職務上の信頼を裏切る行為であるため、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)などと比べても厳しく処罰される枠組みになっています。
他人の物
横領の対象となる物は、他人(委託者)が所有する物でなければなりません。これには、現金だけでなく、会社から支給されているパソコンや事務用品なども含まれます。
金銭については、民法上は占有と共に所有権が移転すると解釈されますが、刑法においては、使途が定められて寄託された金銭、債権取立受任者が取り立てた金銭、集金人が取り立てた売掛代金などは、委託者側に所有権が留保されると解釈されています。
この特別な解釈により、業務上横領罪の客体の中心である金銭についても、罪が成立し得ることが保証されています。
委託信任関係に基づく占有
その財産を自分が占有(実質的に管理)していることが必要です。他人から信頼されて預かっている状態、委託された信頼関係に基づいて占有している状態が必要です。
これは、他人の物を預かったり、管理したりする状態を意味し、その物の利用や処分を自分の判断でできる状態を指します。銀行の集金係がお客のお金を預かる状況や、会社の経理担当者が会社の現金や預金通帳を管理する状況が典型例です。
重要なのは、所有者または権限のある者からの委託に基づいていることです。委託者に委託権限がない場合でも、「委託に基づく占有」が認められる判例もあります。
さらに、詐欺行為によって得た金銭を預金口座で管理していた場合にも、この要件が認められることがあります。これらの事例から、法律は形式的な委託関係だけでなく、実質的な管理状況も重視していることがわかります。
業務上
横領行為が「業務」として行われたことが求められます。ここでいう「業務」は、会社などの仕事に限らず、PTA、ボランティア団体、趣味のサークルといった社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務全般を指します。営利目的であるかどうかは問われません。
この要件が存在することで、単なる横領罪よりも重い刑罰が科される理由となります。それは、業務という信頼関係を背景に行われる横領行為は、社会的な非難の程度が高いと考えられるためです。
例えば、会社の経理担当者が会社の資金を横領する行為だけでなく、町内会の会計係が管理する会費を使い込む行為も業務上横領罪に該当する可能性があります。
横領行為
占有している他人の物を、所有者でなければできないような処分をする行為を行うことが必要です。具体的には、他人の物を売却したり、消費したり、質に入れたり、隠蔽したりする行為が該当します。
顧客から預かった現金を会社に報告せずに着服する、レジ担当者がレジ内の現金を抜き取る、会社の預金管理者が架空の請求書を作成して預金を出金するなど、様々な態様が考えられます。
たとえ被害額が僅少な場合でも、原則として業務上横領罪は成立する可能性があります。ただし、被害額があまりに少ない場合(例えば1円)、処罰の必要性が乏しいと判断されることもあり得ます
単純横領・窃盗罪・背任罪との違い
業務上横領と混同しやすいものに窃盗罪と背任罪があります。窃盗罪は他人の財物を盗む犯罪で、預かっていない他人の物を勝手に取る場合に成立します(例:従業員が金庫から現金を盗む)。
| 特徴 | 業務上横領罪 | 単純横領罪 | 背任罪 | 窃盗罪 | 特別背任罪(会社法) |
|---|---|---|---|---|---|
| 占有 | 業務上の委託信任に基づく占有 | 委託に基づく占有(業務性は不要) | 他人のために事務を処理する者が任務に背く行為 | 占有なし | 会社法上の地位に基づく占有 |
| 行為 | 自己または第三者のために不法に領得 | 自己または第三者のために不法に領得 | 自己または第三者の利益を図る、または本人に損害を加える目的で任務に背く行為 | 占有者の意思に反して財物を自分の支配下に移す | 自己または第三者の利益を図る、または株式会社に損害を加える目的で任務に背く行為 |
| 対象 | 他人の物 | 他人の物 | 本人の財産 | 他人の財物 | 株式会社の財産 |
| 法定刑 | 10年以下の懲役 | 5年以下の懲役 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方(取締役等の場合) |
| 主な適用場面 | 会社の経理担当者による横領、団体会計の不正使用 | 友人から預かったお金の使い込み、拾得物の不法領得 | 従業員によるリベート受領、銀行員による不適切な融資 | 他人の財布を盗む、会社の金庫から現金を盗む | 取締役による会社の資金流用、担保価値のない資産の購入 |
単純横領罪
自己が占有する他人の物を横領する点は共通していますが、業務上の委託信任関係がない場合に成立します。例えば、友人から預かったお金を勝手に使う行為などが該当し、法定刑は5年以下の懲役と、業務上横領罪よりも軽くなっています。信頼の度合いが低い状況での横領行為と位置づけられます。
(横領)
引用元:刑法第252条
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
背任罪
背任罪は他人のために管理している事務について任務に背反し、本人に財産的損害を与えた場合に成立する犯罪です(例:会社役員が権限を乱用して会社に損害を与える取引を行う)。
(背任)
引用元:刑法第247条
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪は必ずしも財物の占有を要さず、金銭的損害を与える目的と結果が重視されます。一方、業務上横領罪は「預かっている他人の物を自分の物のように扱う」点が本質であり、窃盗のように最初から無断で盗む場合とも、背任のように間接的に損害を与える場合とも異なる犯罪類型です。
他人のためにその事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立します。
業務上横領罪との違いは、横領行為の有無です。背任罪は、自己の占有する他人の物を自分の利益を図るために行う場合に限らず、第三者の利益を図った場合や、会社に損害を与える目的で行われた場合にも成立し得ます。例えば、従業員が仕入先からリベートを受け取る行為などが該当し、法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
窃盗罪
他人の財物を窃取する罪であり、占有者の意思に反して財物を自分の支配下に移す行為を指します。
業務上横領罪とは異なり、窃盗罪では、犯人は最初から財物の占有を有していません。例えば、金銭の管理を任されていない従業員が、誰もいない隙に会社の金庫から金銭を盗む行為が該当し、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
(窃盗)
引用元:刑法第235条
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
特別背任罪
会社法に定められた犯罪で、株式会社の取締役などが、自己または第三者の利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、株式会社に財産上の損害を加えた場合に成立します。
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(代表社債権者等の特別背任罪)
引用元:会社法第960条、会社法第961条
第九百六十一条 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
行為者が会社において一定の地位にある人物に限定されている点が、通常の背任罪や業務上横領罪と異なります。
業務上横領における裁判所判例と実刑判決の内容
学校法人預金小切手横領事件(仙台地方裁判所・平成18年2月24日)
学校法人の理事長が、預かり保管中の学校預金小切手を29回にわたり計1億3500万円着服した事件。犯行期間中、被告人は自らの生活費や交際費、親族への資金提供を目的に現金3000万円も横領。
裁判では「組織の最高責任者としての立場を悪用した公私混同」が指摘され、懲役7年・罰金2000万円の実刑判決が下されました。仙台地裁は「身勝手な動機と長期にわたる犯行が組織への重大な信頼侵害」と認定し、厳罰を科した典型例です。
社会福祉法人経営権譲渡を巡る業務上横領事件(東京地方裁判所 令和5年9月6日)
被告人Aは懲役5年6月、被告人Bは懲役3年(執行猶予5年)の判決が下されました。本件は、社会福祉法人Cの理事長であった被告人Aが、医療法人社団DEクリニックの院長であった被告人Bと共謀し、C名義の預金口座からB名義の口座へ約5億6800万円を業務上横領した事件です。
Cの経営権を有償で譲渡する契約の一環として行われましたが、法令上許されず、Cの資金繰り悪化の一因となりました。被告人Aが主導し、Bも経済的利益のために関与しました。被告人Bは被害弁償を行っています。
業務上横領及び有印私文書偽造被告事件判決(東京地裁 令和5年9月20日)
被告人はAの事務局長兼会計責任者及びEの会計責任者として、それぞれの預金通帳と届出印を管理する立場を利用し、約2年半の間に、私的な目的で合計6249万2000円を横領。また、横領の発覚を恐れ、Aの預金残高を実際より多く見せかけるため、A会長D及びその知人Gと共謀し、銀行の預金通帳の取引履歴99件、残高証明書3通を偽造しました。
裁判所は、業務上横領の被害額が高額であり、常習的に行われ、A及びEの会員の信頼を裏切る悪質な犯行であると指摘しました5。文書偽造についても、銀行の重要な信用を害する行為であるとしました。一方で、被告人が起訴事実を全面的に認め反省の態度を示していること、前科がないことなどを酌量すべき事情として考慮しました。
結論として、裁判所は被告人に対し、懲役4年6月の判決を下し、未決勾留日数中280日を刑に算入することを決定。検察官の求刑は懲役6年。横領と文書偽造の両方の罪で有罪とされました。
特に被害額の大きさが刑の重さに大きく影響
実際の裁判で科される刑(量刑)は事案の内容によって様々ですが、特に被害額の大きさが刑の重さに大きく影響します。一般に、被害額が少額で初犯の場合は執行猶予付き判決になるケースが多く、一方で被害額が高額だったり常習的・悪質な場合は実刑(刑務所に服役する判決)となりやすい傾向があります。以下は参考となる量刑の目安です。
- 被害額が100万円以下の場合:多くは懲役刑に処せられても執行猶予が付く
85万円を着服したケースでは懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決)。 - 被害額が数百万円規模の場合:おおむね懲役1~3年程度の実刑が科される
被害額約500万円で懲役2年(執行猶予なし)
700万円台で懲役2年6ヶ月の実刑判決 - 被害額が数千万円規模の場合:懲役3年前後以上の実刑が目安
被害額1700万円台では懲役2年6ヶ月程度~3年の実刑判決(示談の有無で差あり)
被害額4000万円規模では懲役3年6ヶ月の実刑判決 - 特に悪質・巨額な事件の場合
- 長年にわたり会社資金約1億5,000万円を私的流用した経理担当者に懲役7年の実刑判決が言い渡された例
- 銀行員が顧客口座から総額3,000万円を引き出した事件で懲役8年の判決が出た例
- 顧客データを不正利用して1,200万円超の利益を得たIT企業社員に懲役9年の実刑判決が科せられた例
などが報告されています。
業務上横領が起きた際に企業が取るべき対応策
業務上横領は企業にとって深刻な問題であり、適切な対応と予防策の実施が不可欠です。本報告では、業務上横領が発生した際の企業の対応策、予防策、および弁護士依頼のメリットについて詳細に解説します。
業務上横領が発生した場合、企業は迅速かつ適切な対応を行うことが重要です。以下に詳細な対応ステップを示します。
事実関係の確認と証拠収集
横領の疑いが生じた際、最初に行うべきは事実関係の確認と証拠収集です。この段階では、業務上横領が実際に発生したか、横領された金額はいくらか、誰が関与していたか、どのような手口が使われたかなどを徹底的に調査します。証拠となる資料を早期に確保することが何よりも重要であり、本人に事情聴取する前に証拠を揃えておく必要があります。
重要なのは疑わしい社員本人に気付かれないよう極秘裏に証拠を集めることです。証拠確保前に本人を問い質すと、証拠隠滅やデータ改ざんをされる恐れがあるため注意します。金銭の流れを示す書類、電子取引のログ、監視カメラ映像など入手可能な証拠はすべて押さえ、社外への持ち出しや削除ができないよう保全します。この段階で証拠が不十分だと後々の法的手続きで不利になるため、入念に準備を行います
証拠収集の対象としては、口座の入出金記録、PCの履歴、防犯カメラ映像などがあります。特に防犯カメラ映像は、レジの金銭を横領するケースでは決定的な証拠となります。横領の瞬間を複数回撮影できれば、「間違えてポケットに入れた」などの言い逃れを防ぐことができます。
また、顧客からの集金を横領したケースでは、顧客が持っている領収書も重要な証拠となります。証拠収集の際は、周辺従業員への慎重なヒアリングも行いますが、噂を広めないよう配慮することが重要です。この段階で本人に察知されると、証拠隠滅のリスクがあります。
本人への事情聴取
十分な証拠を集めた後、本人への事情聴取を行います。この段階の目標は、本人に業務上横領を認めさせることです。事前に証拠を揃えておくことで、本人が嘘をついても証拠と矛盾が生じ、最終的に事実を認める可能性が高まります。
横領を認めた場合は「支払誓約書」、認めなかった場合は「弁明書」の提出を求めます。支払誓約書は、本人が横領の事実を認めた証拠となり、後の法的手続きでも有効活用できます。
懲戒処分の実施
横領が確認された場合、企業の規律を維持するために懲戒処分を行います。業務上横領の場合は、最も重い懲戒解雇が妥当なケースが多いです。ただし、就業規則に懲戒解雇の規定があることを確認し、手続きを慎重に進める必要があります。不当解雇と判断されるリスクを避けるため、証拠や事情聴取の内容を十分に検討した上で決定します。
社内調査で横領が確認された場合、企業内のルール(就業規則)に基づき懲戒処分を検討します。一般的には、懲戒解雇(即時解雇)相当の重大な背信行為と評価されます。たとえ被害額が少額でも、横領は会社の信用を失墜させる行為のため基本的には厳正に対処します。
懲戒解雇とする場合は、就業規則の規定に則り、懲戒解雇相当の事由があることを社内で適切に決裁し、解雇通知書を交付するといった正式な手続きを踏みます。注意すべきは証拠不十分のまま性急に解雇しないことです。
証拠が弱い状態で解雇すると、後に本人から「解雇無効」や「不当解雇による慰謝料請求」などの訴訟を起こされるリスクがあります。そのため処分を下す前に、社内の法務部門や外部の弁護士に助言を仰ぎ、手続きに瑕疵がないよう慎重に進めることが望まれます。
必要に応じて、調査完了まで当該社員を自宅待機・停職処分とするなど、一時的な措置をとることも検討します。
本人への損害賠償請求
横領の事実が確認できたら、会社として被害額の回収に動きます。まず本人に対し、横領した金銭の返還を求めます。本人の資力を調査し、返済能力がありそうなら内容証明郵便で正式に返還請求を出します。
業務上横領による被害金額は、横領した従業員本人に対して損害賠償を請求することができます。ただし、被害金額が高額な場合、従業員本人の支払能力が不足している可能性もあります。その場合は、給与との相殺や退職金の不支給など、様々な対処方法を検討します。
損害賠償請求には時効があり、「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」のいずれか早いほうとなっています。
判決を得て確定すれば、給与や財産の差押えなど法的手段で回収を図ります。また、横領によって会社が二次被害(信用低下による取引停止等)を被った場合は、その損害についても併せて請求を検討します。いずれにせよ、会社の損失を最小限に抑える努力を迅速に行うことが大切です。
刑事告訴の検討
被害の規模や従業員の態度などを考慮して、刑事事件として対応を進めることも選択肢となります。警察に告訴し、業務上横領事件として捜査・処罰を求めることで、刑事責任を追及できます。刑事告訴は強い制裁となるだけでなく、厳しい対応を社内外に示すことができます。
ただし、従業員が逮捕・起訴されると横領事件の事実も社外に知られてしまうため、告訴には慎重な判断が必要です。刑事訴訟にも時効があり、横領から7年を過ぎると処罰を求めることができなくなるため、迅速な対応が求められます。
刑事告訴は犯罪の再発防止・抑止と社会正義の実現のための重要な手段です。会社として被害届を出すことで、他の社員への教訓ともなり「不正は許さない」というメッセージになります。もっとも、刑事手続きに移行すると被害回復の交渉は一旦ストップしますので、起訴前に示談交渉を行う余地も考えられます。
特に犯人が初犯で真摯に反省・弁済の意思を示している場合、起訴前に示談(被害弁償と引き換えに被害届を取り下げる合意)を成立させるケースもあります。示談が成立すれば犯人に対する量刑が軽減されたり不起訴となる可能性もあるため、会社として回収すべき金額が確保できるなら示談による解決を図る選択肢も実務上はあり得ます。
示談交渉を行う際は、必ず弁護士を通じて慎重に進めるべきです
社内・社外への説明
業務上横領が発生した場合、適切なタイミングで社内・社外への説明を行うことも重要です。特に社内では、同様の不正行為の予防という観点から、どのような不正が行われ、どう対処したかを適切に共有することが有効です。
状況に応じては警察への早期相談も有効です。特に巨額横領や他の共犯者が疑われる場合などは、証拠集めも限界があるため、早めに警察や専門の第三者(デジタルフォレンジックの専門家や探偵事務所等)と連携することも検討します。実際、一部企業では内部不正調査に外部の調査会社を活用する例もあります。
業務上横領を未然に防ぐための予防策
横領が発覚した際には再発防止策の策定も不可欠です。同種の不正が起きた原因を分析し、内部統制の弱点を補強する措置を講じます(例えば「経理担当者を複数配置に変更」「承認フローの見直し」「在庫管理システムの導入」等)。社内で不正が起きた事実は社外にも伝わり得るため、必要に応じて信用回復に向けた対外説明や広報対応も行います。
そして何より、同様の不正が二度と起きないよう社内意識を引き締める契機とします。効果的な予防策を以下に説明します。
内部統制システムの強化
内部統制システムの強化は、横領防止の最も基本的かつ効果的な手段です。具体的には、経理のチェック担当者を複数名にする、定期的に経理担当者を変更する、帳簿残高と現金の額を毎日一致させる、出金伝票を活用するなどの対策が考えられます。
特に「ダブルチェック体制」の導入は重要で、一人の担当者が単独で金銭や物品を扱うことのないよう、複数の目で確認する仕組みを整えることが効果的です。また、定期的な内部監査の実施や透明性の高い財務報告システムの導入も有効な対策となります。
コンプライアンス研修の徹底
従業員の倫理意識を高めるため、定期的なコンプライアンス研修を実施することも重要です。研修では、横領の発生事例や横領をした従業員のその後の処遇(刑事罰や損害賠償請求など)を具体的に紹介することで、横領の抑止力となります。
また、研修を定期的に実施することで、会社が横領を許さないという姿勢を明確に示すことができます。ただし、誠実に業務に励む従業員に不信感を与えないよう、研修の頻度や内容は慎重に検討する必要があります。
現金管理体制の整備
現金は横領されやすい資産であるため、現金管理の体制を整備することが重要です。具体的には、現金は速やかに入金するルールを構築する、小口現金を可能な限り廃止する、入出金履歴を定期的に確認するなどの対策が考えられます。
電子決済やキャッシュレス化を進めることで、現金を取り扱う機会自体を減らすことも効果的な対策となります。
経理業務の透明化とアウトソーシング
経理業務をブラックボックス化せず、透明性を確保することも重要です。経理担当者が長期間固定されることで不正のリスクが高まるため、定期的なローテーションを行うことも検討すべきです。
また、経理業務の一部または全部をアウトソーシングすることで、社内での不正リスクを軽減できます。専門の会計事務所などに業務を委託することで、専門的な知識と第三者のチェック機能を活用できます。
従業員満足度の向上施策
職場の不満が横領の原因となることもあるため、従業員の満足度を高める取り組みも重要です。公平な報酬体系、透明な昇進機会、健全な職場環境の提供などにより、従業員の不満を軽減し、不正行為のリスクを減らすことができます。
また、内部通報制度を設置し、横領や不正行為を発見した従業員が安心して報告できる環境を整えることも効果的です。
業務上横領事件を弁護士へ相談するメリットと具体的なサポート内容
業務上横領の問題に直面した場合、早期に弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。内部調査の段階から法的アドバイスを受けることで、適切な証拠収集や手続きの進め方について専門的な助言が得られ、後々の紛争リスクを減らすことができます。
証拠収集のサポート
弁護士は、会社が業務上横領の事実を明らかにするために必要な証拠を収集・整理するのを支援します。これには、会計帳簿、銀行取引記録、電子メール、監視カメラの映像など、事件の状況に応じて多岐にわたる証拠が含まれます。
弁護士は、どのような証拠が重要となるか、どのように収集すればよいかについて具体的なアドバイスを提供します. また、必要に応じて、会社に代わって証拠収集を行うこともあります。
例えば、弁護士会照会という制度を利用して、銀行などから取引履歴を取り寄せることが可能な場合があります。適切な証拠を収集・整理することで、事実関係の解明をスムーズに進め、後の刑事告訴や損害賠償請求といった手続きを有利に進めることができます。
証拠収集の初期段階から弁護士のサポートを受けることは、事件の真相解明と被害回復にとって非常に重要です.
告訴・告発の手続き
弁護士は、会社に代わって警察や検察に対して業務上横領の被害を申告する告訴状や告発状を作成し、提出する手続きを代行します. 告訴・告発は、犯罪の捜査を求める法的な手続きであり、これを行うことで、捜査機関が事件を本格的に捜査を開始することが期待できます。
弁護士は、事実関係を正確に記載し、必要な証拠を添付した告訴状・告発状を作成することで、捜査機関に対して事件の重要性を伝え、適切な捜査を促します。また、告訴・告発後も、捜査の進捗状況について捜査機関と連携を取り、会社側の意向を伝えるなど、継続的なサポートを行います。
刑事告訴・告発の手続きを弁護士に依頼することで、会社は煩雑な手続きから解放され、本業に集中することができます。
損害賠償請求
弁護士は、業務上横領によって会社が被った損害の回復を目指し、加害者に対して損害賠償を請求する活動を行います。まずは、加害者との間で示談交渉を行い、被害金額の返還や慰謝料などの支払いを求めます。
弁護士は、会社の損害額を正確に算定し、法的な根拠に基づいて交渉を進めます。示談交渉が不調に終わった場合には、民事訴訟を提起し、裁判所を通じて損害賠償を請求することになります。
訴訟においては、証拠に基づいて会社の損害を立証する必要があり、弁護士は訴状の作成、証拠の提出、法廷での主張など、訴訟手続き全般をサポートします。損害賠償請求を通じて、会社は経済的な損失を回復し、加害者に対して法的な責任を追及することができます。
従業員の解雇手続き
弁護士は、業務上横領を行った従業員に対する懲戒解雇などの解雇手続きについて、法的なアドバイスを提供します. 従業員の不正行為を理由に解雇する場合、労働契約法や就業規則に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。
不適切な手続きで解雇した場合、従業員から不当解雇として訴訟を起こされるリスクがあります. 弁護士は、解雇理由の正当性、解雇手続きの適法性などを確認し、会社が法的なリスクを負うことなく解雇手続きを進められるようにサポートします。
具体的には、就業規則の確認、解雇理由書の作成、従業員との面談への同席などを行います. 適切な解雇手続きを行うことは、会社を守る上で非常に重要です。
再発防止策の策定支援
弁護士は、会社が今後同様の業務上横領事件を発生させないための再発防止策を策定するのを支援します。
弁護士は、今回の事件の原因や背景を分析し、会社の内部統制の দুর্বলな点や改善すべき点を洗い出します. その上で、具体的な再発防止策を提案します。例えば、会計処理の厳格化、複数担当者によるチェック体制の導入、内部監査の実施、従業員に対するコンプライアンス教育の実施などが考えられます。
弁護士は、これらの対策が法令や会社の状況に適合しているかを確認し、実効性のある再発防止体制の構築をサポートします。再発防止策を講じることは、会社の信頼性を高め、将来的な損失を防ぐために不可欠です。
業務上横領事件に強い弁護士を探す具体的な方法
日本の弁護士会が提供する弁護士検索サービス
日本弁護士連合会(日弁連)は、全国の弁護士を検索できるオンラインサービスを提供しています 。
- 日弁連の弁護士検索: 現在登録されているすべての弁護士の基本情報(氏名、所属弁護士会など)を検索できます。弁護士が実在するかどうか、どの弁護士会に所属しているかを確認する際に便利です。
- 弁護士情報提供サービス「ひまわりサーチ」: 取扱業務などの一定事項から該当する弁護士を検索することができます。キーワードに「刑事事件」や「企業法務」などを入力することで、関連する分野に注力している弁護士を探すことができます。
ただし、ひまわりサーチへの登録は任意であるため、すべての弁護士が登録されているわけではありません。また、掲載されている情報は弁護士自身の自己申告に基づいているため、詳細は各弁護士に直接確認する必要があります。
法テラスなどの公的機関における弁護士紹介制度
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困窮している方などを対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えなどの支援を行っています。通常の法律トラブルの場合、直接弁護士を紹介してくれるわけではありません。しかし、法テラスと契約している弁護士を紹介してもらうことは可能です。
ただし、紹介される弁護士の得意分野が必ずしも自分の悩みに合致するとは限らない点に注意が必要です。
- 犯罪被害者支援: 相談者が犯罪被害者である場合、法テラスは弁護士を紹介してくれることがあります。会社が業務上横領の被害に遭った場合なども、法テラスに相談してみる価値はあるでしょう。
- 弁護士会の法律相談センター: 各弁護士会も、法律相談センターを設けており、有料で法律相談を受け付けています ।必要な場合には、弁護士を紹介してもらえることもあります。
刑事事件や企業法務に強い法律事務所のウェブサイト検索
インターネット検索は、業務上横領に強い弁護士や法律事務所を探す上で非常に有効な手段です 。
- 弁護士紹介サイトの利用: ベンナビ刑事事件、刑事事件弁護士PRO、企業法務弁護士ナビなどの弁護士紹介サイトも、専門分野や地域で絞り込んで弁護士を探すのに役立ちます。
- キーワード検索: 「業務上横領 弁護士」、「刑事事件 強い 弁護士」、「企業法務 弁護士」などのキーワードで検索することで、関連性の高い法律事務所のウェブサイトを見つけることができます。
- 事務所ウェブサイトの確認: 見つけた法律事務所のウェブサイトで、取扱業務や弁護士のプロフィールを確認します。業務上横領事件の取り扱い経験や実績が明記されているか、刑事事件や企業法務に注力している弁護士が所属しているかなどを確認しましょう。
表2: 弁護士を選ぶ際に考慮すべき主な要素
| 要素 | 説明 | 重要度 |
|---|---|---|
| 経験と実績 | 業務上横領事件の取り扱い経験と成功事例 | 専門知識と効果的な戦略の指標 |
| 分析力 | 複雑な事実関係や証拠を分析する能力 | 事件の全体像把握と強力な弁護戦略に不可欠 |
| 交渉力 | 示談交渉の能力 | 刑事事件化の回避や有利な解決に影響 |
| 刑法・会社法の知識 | 刑事法と会社法に関する深い理解 | 多角的な視点からの法的アドバイスに必要 |
| 会計知識 | 会計帳簿や財務諸表を理解する能力 | 横領の手口や被害額の特定に役立つ |
| コミュニケーション能力 | 依頼者との円滑な意思疎通 | 信頼関係構築と効果的な連携に不可欠 |
| 秘密保持と倫理観 | 依頼者の秘密を厳守し、高い倫理観を持つこと | 安心して相談できる基盤 |
| 迅速な対応と可用性 | 緊急時にも迅速に対応できること | 機会損失を防ぎ、早期解決に繋がる |
| 信頼性と相性 | 安心して相談できる信頼関係 | スムーズな事件解決に不可欠 |
| 費用と支払い方法 | 弁護士費用の明確な説明と支払い方法の柔軟性 | 経済的な負担を考慮した選択 |
| 事務所の所在地とアクセス | 面談の利便性 | 必要に応じて対面での相談がしやすい |
まとめ
最後に付け加えると、業務上横領の問題は「発生後の対処」以上に「発生前の予防」が重要です。弁護士は事後対応だけでなく、社内規程の整備や内部監査体制構築についての助言など予防法務の面でも力を発揮します。自社の内部統制に不安がある場合は、顧問弁護士や専門家の力を借りて体制を見直すことも検討してください。
不正の芽を摘み、健全な企業風土を維持することが、ひいては会社の信頼と財産を守ることにつながるのです。